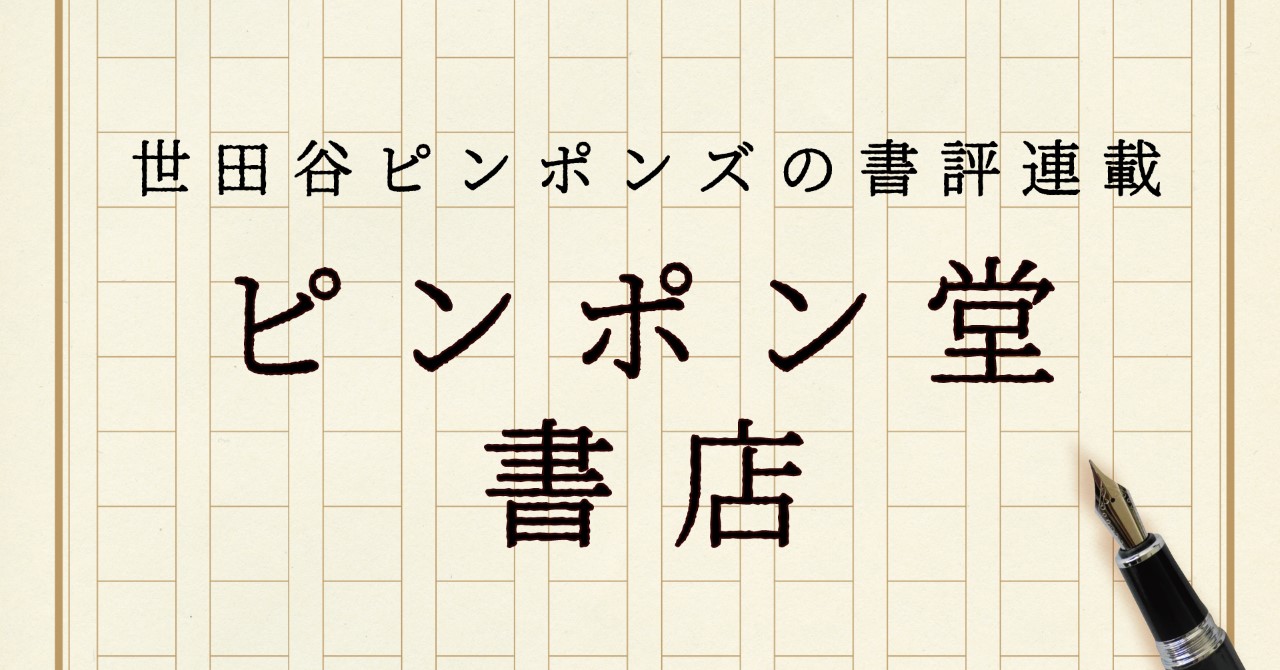世田谷ピンポンズが毎月気になった書籍を、彼の持ち味である、生活感のあるノスタルジーが散りばめられた文章でご紹介。最終回は又吉直樹『東京百景』。
これまでの連載はこちらから
それでも僕たちはこの街に憧れて、この街で生きて

文/世田谷ピンポンズ
死にたくなるほど苦しい夜には、これは次に楽しいことがある時までのフリなのだと信じるようにしている。(『昔のノート』)
又吉直樹『東京百景』の中で特に好きな一節のひとつだ。音楽を続けていくなかで、何度もこの言葉に救われてきた。又吉さんの言葉は走り過ぎず、かといって遠くからこちらを冷ややかに俯瞰することもなく、ただいつも緩やかに並走してくれる。
二〇二〇年末に初の随筆集『都会なんて夢ばかり』(岬書店)を出した。些細な思い出の断片をひたすら連ねた、見ようによっては全く独りよがりの自分語りを、それでもしてみようと思ったのは、版元である岬書店・島田潤一郎さんが何かに書いた「個人的なことを突き詰めることによって、はじめて、普遍的なことが浮かび上がる」という言葉に励まされたのと、『東京百景』で又吉さんがしたように僕は僕なりの東京を書き綴ってみたかったからだ。東京での十年は自分の人生にとって本当に特別な時間だった。
慣れない執筆作業中、傍らに『東京百景』を置いて何度も読み返した。本のそこかしこに確かに自分にも身に覚えのある様々な感情が埋まっていた。それらに明確な名前はついていなかったけれど、僕には実感があった。訳が分からなくなってどつぼにはまりそうになっても、本の中にいつかの記憶の断片を見つけることで何度も背中を押された。
小さく珍妙な形をしたエアコンが先輩の殺風景な部屋の窓際にポツンと置かれている。開け放しの押し入れにはくしゃくしゃになった服が積み上げられ、横には本棚代わりのクリアケースが二つ乱雑に転がっている。シンクはどれくらい前から使っていないのだろう、先が茶色く変色した蛇口はカラカラに乾いている。
「このエアコンさ、室外機がないうちのような部屋でも取り付けられるんだよ。西友って何でも売っているよな」
ろくすっぽ掃除もしないから埃が堆積し、全体的に白みを帯びたエレキギターをピックでシャリシャリやりながら先輩が笑う。エアコンは効いているのかいないのか、よくわからなかった。
「こんな形のやつ、初めて見ましたよ」
「な。結構すごいよね」
コンビニで買ったミミガーをコリコリ。
そろそろ帰り支度だと腰を上げると、
「ほそや、もう少しだけいてくれよ。な。お願いだよう」
先輩は手を前ですり合わせ拝んで見せる。
「明日もバイトで会うじゃないっすか。おやすみなさい」
細いらせん状の階段は踏みしめるたびにミシミシ音を立てる。薄暗い共同玄関を抜けて外に出ると、まだまだ粘り気の強い東京の夏だ。アパートの外壁は繁殖力の強そうな雑草のツタで覆われている。天然の緑のカーテンだ。その割に先輩の部屋は全然涼しくない。どころか、むしろ暑くて息苦しかった。静まり返った住宅街を三軒茶屋まで歩く。少しして先輩は音楽をあきらめ、地元へ帰った。
室外機と同じ数だけエアコンがあるのだ。涼しい部屋で眠る人がいるのだ。室外機の個数は、そのまま僕の敗北の数でもあった。(『東京のどこかの室外機』)
井の頭公園の七井橋の上で恋人と出会った。春。近くでは漫画を異様な迫力でもって読み聞かせるパフォーマンスをする人、にゃあ、にゃあとギターを弾きながら歌うおっさん、沢山のカップルや家族連れ。池の周りを連れ立って歩く。弁天堂に差し掛かると「後輩にお守りを買いたい」と彼女が言った。花のにおいがした。道が少しぬかるんでいた。水面がキラキラ光って眩しかった。
生まれて初めて自作の歌を聴かせたのも彼女だった。彼女はヒップホップやR&Bが好きだったから、僕の作るような歌は聴いたことがなかったに違いない。
彼女は、「音楽の良し悪しは分からないけど、君が言いたいことや、何かをやりたいんだってことは痛いほど分かったよ」と言った。
彼女も僕もどこか似たような淋しさと高揚を纏っていたから、なんだか妙に気が合って、いつのまにか三軒茶屋の小さな六畳間で一緒に暮らすようになった。良いことがあれば一緒に喜び、甘ったれているときには容赦なく怒ってくれた。僕が一人で夢想していたことはすべて彼女が叶えてくれた。
僕が憂鬱な状態の時も彼女は独りで唄いながら踊っていた。とにかく明るかった。毎晩、僕を散歩に送り出し、川で泣いて帰ってくる僕に梨など季節の果物をむいてくれた。(『池尻大橋の小さな部屋』)
『池尻大橋の小さな部屋』に住む又吉さんの恋人はその後体調を崩してしまい、東京を離れる。
なぜ、あんなにも身勝手で横暴で相手に寄生するような日々を過ごしたのか。若さを言い訳にしていた。いつか恩返しができる日が来ると噂で聞いていた。本当はこんなはずじゃなかった。(『池尻大橋の小さな部屋』)
優しさに甘え、自分を一番大事に思ってくれている人を簡単に傷つける。反省して学んだつもりになってもまた性懲りもなく繰り返す。僕たちはいつも後悔してばかりだ。思い出すことで自分を納得させてみる。思い出すことしかできないことを情けなく思ったりもする。
僕たちはなんとかこの街で生きてきた。起こりえたかもしれないことや起こってほしかったことが、いつのまにか自分の脳内で勝手に都合のいい現実になることもあるだろう。でもそんな独りよがりの感傷が時折、顔を出しても、恥じることはない。思い出すことでいまを生きていけると本気で思えるときがいままでに何度もあった。
僕たちはセンチメンタル過多だ。猫背の背骨には大抵感傷がへばりついている。
過剰なセンチメンタルを笑う奴は、ナイーブな心をバカにする奴は、センチメンタルが生み出す攻撃力を、ナイーブがもたらす激情を知らない。(『代田富士見橋の夕焼け』)
感傷にいつも関わり合ってばかりはいられないけど、だからってそれを無視して生きていくことはできない。
前方に視線を投げながら、いつかの風景を思い出していることが本末転倒だなと思いはするが、ルール上は問題ない。この散歩のルールは僕が作ったものだから。(『代田富士見橋の夕焼け』)
いくら前フリだと思っても、つらい現実の後に必ず幸せな出来事が待っているとは限らない。
それでも、後ろを向くのだって、いつもちゃんと前を見ていなくっちゃできないし、とか嘯いてみる。
でも本当はそんなことはどっちでもいい。
僕たちは喉が渇いたあとに飲む水の美味しさを知っているし、どこにだって自分のペースで歩いていける。
投稿者プロフィール
- テレビ雑誌「TV Bros.」の豪華連載陣によるコラムや様々な特集、過去配信記事のアーカイブ(※一部記事はアーカイブされない可能性があります)などが月額800円でお楽しみいただけるデジタル定期購読サービスです。