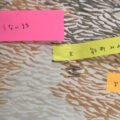※本連載はTV Bros.4月号沈黙の艦隊特集号掲載時のものです
ヴィム・ヴェンダースと役所広司のファンとして私も例に漏れず映画『PERFECT DAYS』を心から楽しみにしていたことには違いないのだけれど、鑑賞後、「ねえ観た!? 超良かったよね!」と話しかけてくれる友に、曖昧な返事をしている自分がいた。
確かに良いところはたくさんあったのだけれど、それを相殺してちょっと総合的にはマイナスな印象が残るほど、ツッコミどころの多い作品だったのだ。周囲から聞く反応やSNS上の感想を見ていると”おおむね好評”のようである。なぜこの作品を彼らが好ましく思ったのか、というのも十分に分析済み且つ理解できている。前提として作品のクオリティの話をするならば、テーマに対して十分な予算とスタッフ・キャスティングを実現させ、画面の単純な豪華さではない真のリッチさとはなにか、をちゃんと思わせるクオリティを引き出しているし、なによりいち映画ファンとしても、ヴィム・ヴェンダースが現代の私達が住んでいるTOKYOを彼の美学とともに切り抜いてくれたこと、役所広司との神聖なほどにPureな相互関係、かれらがこの平山というキャラクターを心から愛することで生まれたこのにじみ出る幸福感、脇を固める名優たちの貴重なすがた、日々を生きるルーティーンを木漏れ日という素朴だが二度と同じ形にならない光の連作に結ぶいじらしさ、劇中音楽のノスタルジックの塩梅……こういう、歓喜のポイントがあふれている素敵な新作映画に出会えたことを大前提嬉しく想う。だが、このごく真っ当な感想にすら、どこか、「そう言わされている」という感覚がつきまとう。こんなに丁寧に作ってくれたなら、一通り肯定しなければ。これを楽しんでいるみなさんといっしょに、私も「素敵だったね!」って言いたい。だってきっとこの映画はあくまで善性にのっとって作られたものなのだから。この世界には資本主義のためでしかないくだらない映画が山程あるのだから、こういう作品を最低限肯定しないとバランスが悪い……そういった、自分自身を社会的存在として捉えた際のバランサーとしての視点が私には強固にまとわりついている。そう、肯定したい。だけれど、もしもここで目を見られながら、『PERFECT DAYS』めちゃくちゃよかったよね! と問われたら、多分絶対に、目をそらしてしまう。その理由をここには書いておきたいと思う。
人々に憧れられはしないトイレ掃除という地道な仕事を毎日丁寧にこなしながら、古本屋で買い集めた本と、大事に育てている観葉植物、カセットテープで聴く古いロック・ミュージック、行きつけの小さな飲み屋、休憩時間に見上げる木漏れ日。平山の日々は毎日代わり映えがしないけれど、それでもわずかに異なっていて、そのひとつひとつの小さな違いや、違わないということ自体が、彼に差し込んでは消えていくささやかな光になっていく、といった感じの話を想像していたとして、(もちろん想像を裏切られることは時には良いことなのだけれど)いや、平山に巻き起こるささやかなハプニング、7割ぐらい、外部からやってくる或いは既に存在している、”女性キャラクターからの刺激”だったな、と思う。はじめのほう、気の所為かと思いながら見ていたが、とある女性キャラクターが文脈を絶妙に裏切ってキスをしたシーンで、私の心のシャッターがガラガラと降りるのがわかった。これはなにも映画内でキスをするなという話ではない。彼女がキスという行動に出る必然性が描ききれていないことにショックを受けた。
ステレオタイプな大和撫子を避けた結果選ばれたであろうアオイヤマダさんのキャラクターはとても魅力的で、さらに言うと”2020年代のTOKYO”らしくもある。だが、これはこれで別のステレオタイプを見せられてはいないか? と疑問が残る。それは、彼女以降に出てくる他の女性キャラクターたち……ぼっち飯をするいかにも”OL”な制服を着た女性・疲れた下町の男たちを飄々と癒すバーのママ(石川さゆり)・突然訪ねてきて平山の生活を掻き乱す姪っ子などが、皆それぞれにどのようにつくられたキャラクターなのかをなるべく色んな可能性の上で想像してみると浮かび上がるひとつの共通点からも言える。このキャラクター達はそれぞれ、ああこういう人いるよね、と全く思えないわけではないが、絶妙にリアリティに欠けている。平山に程よい刺激を与えるためにつくったキャラクターだと考えると余りにも合点が行ってしまうのである。要するに、映画自体のルックの美しさや役者のクオリティなどを一度加味せず冷静に見ると、構造的には男性主人公のライトノベルに近い印象を受けたのだ。
物語など誰かが作ったフィクションなのだから、主人公を立てて、その人物の周りから他キャラクターが刺激を与え、それによって主人公に影響や変化が起きていく……という作りになっていることは全く珍しいことではない。それどころか、ほとんどの物語がそうした順序で作られているだろう。しかし、冷静になると、この映画における女性キャラクターたちの表層は、あまりにも「差し色」のような扱いではないか? と、どうしたって気がついてしまう。これはおじさんたちが企画しておじさんたちが作った、おじさんのための映画だ。出てくるキャラクターはおじさんが見ていて気持ちいい範囲の個性を持ち、役所広司演じる平山を不快じゃない程度に翻弄し、その全員が平山にうっすらとした好意を抱いている。私が自分の作る作品でとある女性キャラクターに対してしっくりこない気持ちを別の映画監督に相談した際、「その女性キャラ、ウサギとかじゃだめなの?」と問われたことを思い出した。その時私は、「………いや、ウサギでもいいですね」と、答えた。聞かれるまで人間の女性でないといけないと思いこんでいたのだが、たしかにウサギでもよかったのだ。『PERFECT DAYS』で平山の近くでぼっち飯をしているOLはおそらく孤独な者同士の無言の共鳴を表したいのだろう。……サラリーマンのおじさんではだめだったのだろうか。目が合う/合わないの隙間にほんの少し差し込まれる「ドギマギ」としたニュアンスに、ああ、女性は弁当を食べているだけでも「意識」されるんだ。と悲しくなる。平山の家を突然訪ねる姪っ子は、家に馴染めず本の世界に浸ったり、平山の仕事を手伝ったりと、彼の価値観に共感する者として描かれる。子ども時代の平山の孤独を暗に表現しているのだろうか。……甥っ子ではいけなかったのだろうか。甥っ子のほうが、より近い温度で彼の孤独を暗喩することができたのではないだろうか。姪っ子の着替えを見てしまいそうになって「ドギマギ」したり、「意識」する平山を見るたびに、胸の奥が冷えていくのが悲しかった。甥っ子だったら、抱きしめたとき、平山が子どものころの平山自身を抱きしめたようなカタルシスが得られたのではないだろうか、と。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ