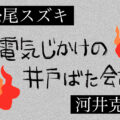様々な人に「推し」や「推し活」について語ってもらう「推し問答!~あなたにとって推し活ってなんですか?」。
昨今、マンガや小説、映画、舞台、あるいはCMなど、様々な場所で「推し(活)」がテーマにされたものが増えています。そんな一大「推し活」ブームの中「推し活」をテーマにした展示も開催されているようです。しかも、大学内の博物館で。それが、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館(通称「演博(エンパク)」)で行われている「推し活!展―エンパクコレクションからみる推し文化」【8月6日(日)で終了なのでお急ぎを!】です。
エンパクは演劇に関するものを収蔵している博物館で、今回の展示は、膨大な資料の中から、観客、ファンの「集める」「共有する」「捧げる」「支える」の4つ、つまり「推し活」的な視点から演劇の歴史を紐解いています。
今回の展示は、主に江戸時代の歌舞伎から戦後のスター、そして現代に至るまでさまざまな「推し」に夢中になり愛を注いできた市井の人々の歴史を垣間見ることができます。
何かを「推す」ことは、今も昔も意外と変わらないもの。とても楽しい展示です。
本展示のディレクションをつとめた早稲田大学演劇博物館の赤井紀美さんに、お話を伺いました。

(左:藤谷千明 右:早稲田大学演劇博物館の赤井紀美さん)
取材&文/藤谷千明 撮影/米玉利朋子(G.P.FRAG inc) 題字イラスト/えるたま
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ