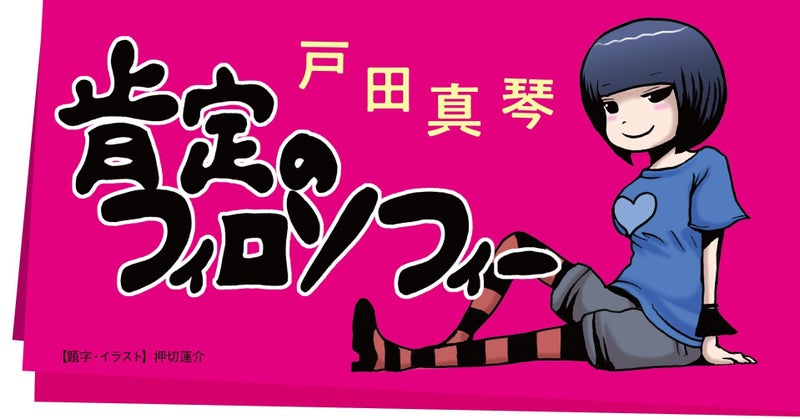今年の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が最高傑作だという噂を聞きつけ、見に行ってきた。「ドラえもんを見るとのび太みたいになってしまうから見てはいけない」といって幼少期から手塚治虫のブッダを読まされていた私にとっての人生初ドラえもん映画である。メインキャラたちの個性あふれる活躍と魅力的なゲストキャラクターたち、よく練り込まれて矛盾のないプロットと嫌味がなく真っ直ぐなメッセージ、何より「絵画の中に入り込む」という設定を存分に活かした演出に胸がどきどきして止まらなかった。
鑑賞する子どもたちの未来に祈りを託し、同伴した大人たちの心になつかしい自由を思い出させる創作讃歌の物語で、優れた娯楽映画としての大事な要素が詰め込まれている噂に違わぬ傑作だった。
映画をつらぬくメッセージはとてもシンプルで、「大好きだと思いながら描いた絵は、うまい絵よりもずっと素晴らしい」というものだった。そりゃあ初めてものを作ってみた頃は上手い下手なんて気にしていなかったかもしれないが、へたくそな作品を笑われ、インターネット上に上げても反応に乏しく、なんだって「うまい」人がどんどん力を得ていく社会の中を諦めながら生きてきた私達大人には、納得しつつも綺麗事にしか思えない話だ。
それでも、物語がほんとうによく作り込まれ、キャラクターたちが感情を動かしながら映画の世界を奔走するところを追っているうちに、そのメッセージが素直に染み込んでくる仕組みになっている。
アニメ映画はなんだってできる。作った人が「これこそが素晴らしい」と信じているものを、物語の中で最も強くて魅力的なものとして描くことで、見ている人はその素晴らしさを受け取ってしまう。誰かの「大好き」という気持ちによって描かれた絵画がお話の中でも正式に最も強いカードとして機能するという事の顛末は、創作=世界を一つ手作りすること、それ自体の持つ秩序を逸脱した無限のパワーを表しているようで、心が震えた。
愛と喜びのためにあたらしいルールをつくろう、直接今すぐに世界を変えることができなくても、君がつくりだすその手の中の世界のなかでは、君の信じる愛と喜びが一番強いことにしよう。そういう新しい希望を見るとき、この世界に美しいことがほんとうに絶えることはないのだと思える。
—
今回で、TV Bros.で書き続けてきた「肯定のフィロソフィー」も一旦の区切りとなる。2018年から連載を続け、これまで持った連載の中でも最も長く続けてきたうえ、大衆誌という点からたくさんの方に感想をいただいてきたかけがえのない連載だった。
連載を始めた頃は前職であるAV女優業の真っ只中にいたこともあり、普通に自分のフィールドで文章を書いているだけでは出会えなかったたくさんの読者に出会わせてくれた。高校の頃の国語の先生から連載を読んでいると手紙をもらったこともあったし、大学の頃に好意を寄せていた同級生に数年越しに連絡をとってみた際には「昔から購読してたTV Bros.に連載が載っていておもしろく読んでいた」と返事が来て驚いたこともあった。『万引き家族』の映画評を書いたときには是枝裕和監督自ら称賛の言葉をSNSに書いてくださったこともあったし、普通にしていたら会うことのない著名人の方々から言葉をいただいたこともたくさんあった。何より、毎月(TV Bros.が隔月化してからは隔月で)フリーテーマで必ず書く場所があるということ、雑誌という形態でふと手に取った誰かの目に言葉が入ることはこの紙の雑誌が衰退している時代においてとても得難いよろこびだったことをよくわかっている。だからこそさみしい。
2018年、ただの映画評がバズりがちなAV女優だった私に声をかけてくれたのは当時の編集長だった木村氏で、ライターの平田真人さんとカメラマンの山田涼香さんをつれて原宿にある事務所へ取材に来た日をよく覚えている。KAI-YOUで映画レビューとお悩み相談を融合させた連載をしていたのを読んだ木村氏が、突然本誌にカラー見開きでのインタビュー掲載を提案したのだった。その記事で平田さんがつけてくれた「肯定のフィロソフィー」というキャッチコピーをタイトルにし翌月から始まった当連載では、毎月指定された文字数の2000字を全く守らず倍ほどの分量を提出し、デザイナーさんの苦心によってなんとか詰め込んでもらい、毎月休むこと無く持論を語ることとなった。
映画や舞台やドラマや音楽ライブなどポップカルチャーへの批評をはじめ、物言うAV女優としての苦心の仕事記録や、小説や映画を制作する際の息抜き的な個人的散文など、戸田真琴から生まれるテキストのありとあらゆる側面を吸い込んできたこの連載は、私にとっては一言では言い表せない複雑な業をもったものとなった。
「肯定のフィロソフィー」という言葉には、当初私の人生の流儀であった、「いつかすべてを肯定する」という思いが込められている。いいことばかりではないけれど、それを「どう見るか」こそが私が私たる唯一の意義であり、どんなにどうしようもない出来事にも、肯定できる角度を探して最後にはそれで良かったと言い切りたい。この世界に生まれてきたことはまず正しくて、生まれないほうがよかったものなどないのだと私が証明したい。それが私の人生をつらぬく願いで、この連載を通じてそのとき出会ったことのひとつひとつを肯定するための計算式のようなものを言葉で書いていこうと思っていたのだ。
連載を始めた当初、発端となった木村氏は夢を語った。この連載の書籍化の際は「映画を超える映画評」と帯に書いて売り出そう、『アフター6ジャンクション』のゲストに呼ばれて宇多丸さんと語り合ってほしい、と。思えばサブカル界隈でバズりつつあったあの頃の戸田真琴には、たくさんの人が夢を託そうとしてくれた。所属していたメーカーでは会長や社長との会食が何度も組まれ、ラジオやテレビの仕事をいただいたりと様々なパイプを作ろうと苦心してもらっていたし、GEOとのコラボレーションで公式YouTubeチャンネルを持たせていただいたり、映画を監督する企画を持ってきてくださって大手の映画プロダクションをプレゼンで回ったりもした。さまざまなメディアの方が声をかけてくださり、連載や書籍の企画、番組のオファーをいただいたりなど、華やかな世界の始まりを予感させる流れに満ちていた。
文章を通じて戸田真琴を知ったたくさんの大人が、「この方向で売っていこう」と意気込んでさまざまなアイデアをぶつけてくれた。すべてが実現に至ったわけではないし、あまのじゃくで偏屈な私はいくつの期待を無下にしてきたか数え切れないが、お話をいただくことは、間違いなく私にとってまぶしいことだった。
私は社会に向いていない。多くのつながりを持ち、知名度を上げたほうがいいのだということがどんなに頭でわかっていても、今違和感があることをしないということ、やろうとこころから思えないことは身体が動かなくて結局できないということ、そういう感覚のほうを優先することしかできない難しい人間だ。もっとわかりやすい存在に自分自身をデフォルメできたら、今いる場所はまた違っていただろう。だけれど、できないものはできないのだということもそろそろ深くわかってきて、爆発的には売れない代わりに今日も幸福である。何も失わなかった。この連載を始めた頃よりも今が幸福であることだけはあまりにもたしかなことで、そこに至るすべてをこれからもあらゆる形で文字にしていかなければいけないと思う。文字になるべきことは文字になるだろう、あなたが読むべきことはあなたがいずれ読むだろう、そう思いながら7年の連載を一旦区切るためのテキストを書いている。