文/世田谷ピンポンズ 題字イラスト/オカヤイヅミ 挿絵/waca
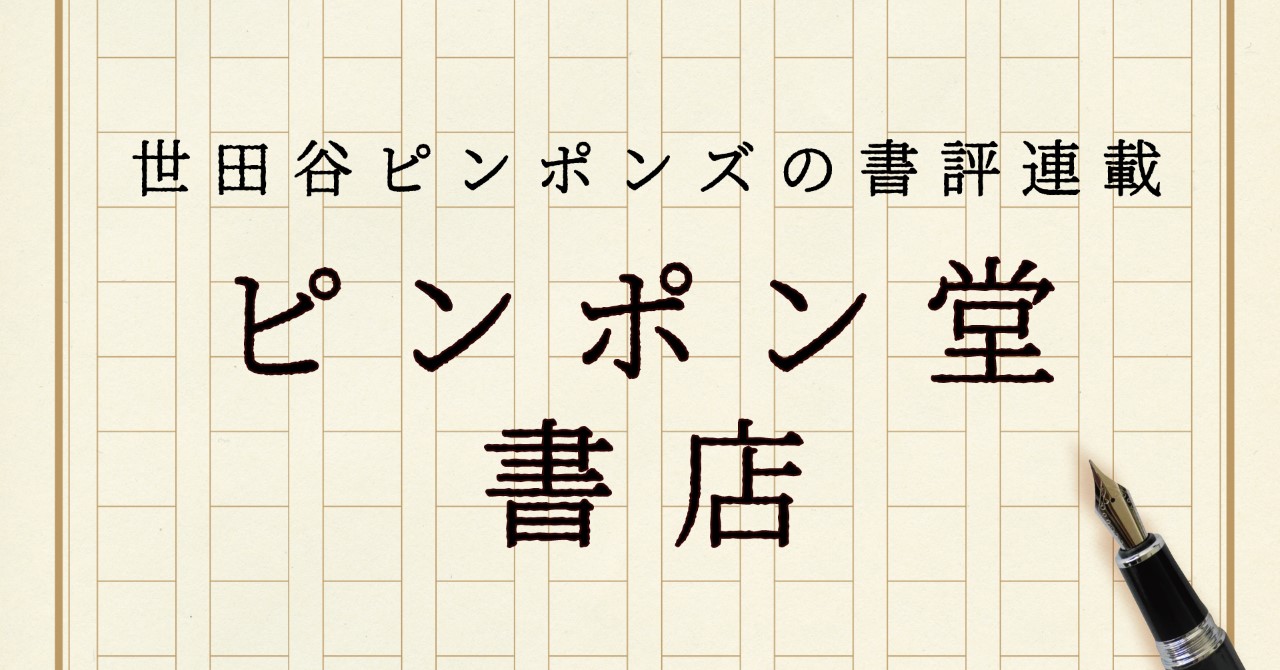
- 【最終回】又吉直樹『東京百景』それでも僕たちはこの街に憧れて、この街で生きて【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】
- 大島弓子『秋日子かく語りき』取り戻せないものはいつだって眩しい【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】
- 松本大洋『東京ヒゴロ』 人は表現を生きるのか【世田谷ピンポンズ連載2023年4月】
京都御所の周りの砂利道に一本の轍ができている。ここを通る幾台もの自転車が作った道である。この街に住んでもう十年。僕は轍に沿って自転車を走らせる。対向車が来たら一旦轍を外れ、砂利道を走る。全然走れないわけではないけれど、轍と比べたら雲泥の差だ。対向車が通り過ぎたらすぐに轍に戻る。慣れたものだ。遠くのほうで警報とともに自動アナウンスが流れている。御所の周りをぐるりと囲む水路を飛び越えて塀のところへ近づいた者がいたのだろう。飛び越えた瞬間だったか、壁に触れた瞬間だったか、とにかくすぐに警告のアナウンスが流れるのだ。僕も昔一度やってしまったことがある。
初めて京都御所を訪れたのは高校の修学旅行のときだった。栃木の高校の共通ルートだったのか、県内の高校のほとんどが同じ時間に御所の周りに集まっていた。他の学校に見知った幼馴染の顔を見つけては、そこかしこで沸き立っている。
「シバタだ。シバタ! まじウケる!」
隣町にある学校の女子生徒たちが騒いでいる。うちのクラスのシバタ君に沸き立っている。というか、シバタ君は嗤われている。確かにシバタ君は普段からクラスでも浮いているほうではある。髪をオールバックになでつけ、顔はどこかマコーレー・カルキンを彷彿させた。行きの新幹線の中では皆が駄菓子に舌鼓を打っているなか、ひとりだけシナモンをかじっていた。アウトローというには線が細すぎるきらいがあったが、シバタ君は揺るぎなき自分を持っている人だった。だからこそ高校ではコソコソ馬鹿にされることになり、揶揄されることになる。
確実にいま、シバタ君は嗤われている! そう思った瞬間、シバタ君は女子生徒たちに向かって高らかに片手を上げると、それを拳銃みたいな形にして振り下ろした。
「バシュンッ」
見えない弾丸が飛んでいく。
どんなに嗤われても自分のキャラを貫くことのできるシバタ君が僕は心底恐かった。恐かったから彼を嗤うことでしか彼と関われなかった。
僕とササキは旅館の廊下の端にある水飲み場へと歩いている。廊下にはシャンプーの残り香と湯気と高揚感だけがある。薄い壁の向こうで女子生徒たちが恋バナで盛り上がっており、ロビーの小さなテレビでは日本代表の試合が流れていて、いまちょうど柳沢敦がゴールを決めたところ。
「Kさんのお風呂上がりの姿を見に行こうぜ」
ササキがニマニマ笑う。
「やめとこうぜ」
僕はかっこつけている。
「別にのぞきに行こうって言っているわけでもないのに。お前って、情けないよな」
そう。僕は情けないのだ。だから結局気持ちも伝えられなかった。
僕とササキだけが修学旅行に電動シェーバーを持ってきている。そんなところばかり、嫌なところばかり、あっという間に大人になっていく。
部屋に戻ると、さっき勢い込んで女子の部屋に向かったはずのアラカワとヤスダがちんまり座っている。
「全然ダメだったよ」
僕たちは笑う。しけた匂いのする布団でみんな一緒に眠る。

この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ




