文/世田谷ピンポンズ 題字イラスト/オカヤイヅミ 挿絵/waca
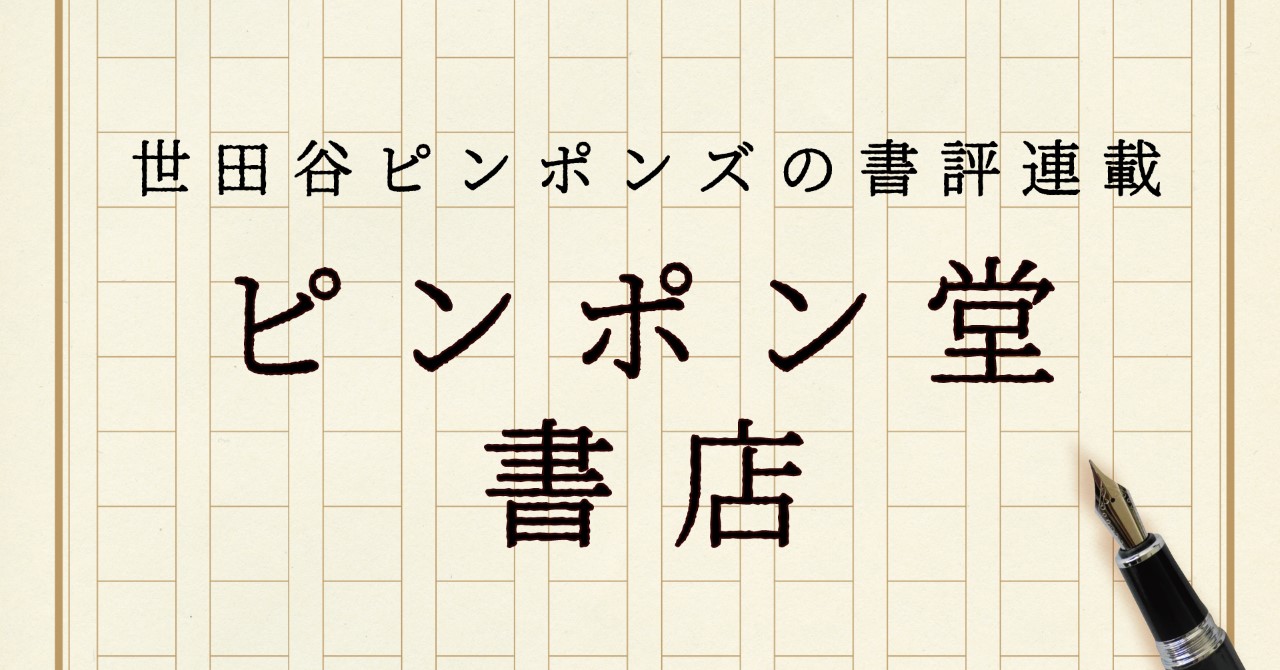
- 【最終回】又吉直樹『東京百景』それでも僕たちはこの街に憧れて、この街で生きて【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】
- 大島弓子『秋日子かく語りき』取り戻せないものはいつだって眩しい【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】
- 松本大洋『東京ヒゴロ』 人は表現を生きるのか【世田谷ピンポンズ連載2023年4月】
昼下がり、暖房のきいたアパートの一室で僕は思わず手をこすり合わせる。
ヘルシンキの港はもうすぐ夜が白々と明けようとしている。遠くの方で大きな貨物船が汽笛を鳴らし、たまに通りかかる車のヘッドライトがまばらに暗闇を照らす。そこにいる人たちの姿までは見えないけれど、眠い目をこすって、たくさんの港湾労働者が働いているのだろう。きっと彼らの吐き出す息は真っ白で、マスクをしている人のメガネは曇っているに違いない。彼らが濡れたアスファルトの上をゴム長靴で歩き回っている姿を想像してみる。パソコンの無音の画面越しに確かに人の息づく気配を感じる。
丸めた両の掌に温かい息を吹きかける。寒さが痛さに変わるその感覚を、夜明け前に起きて働くときの何ともいえない気怠さを、遠くの街に住む僕も確かに知っている。
世界がコロナ禍に入って久しい。
初期のころの所謂、自粛生活と呼ばれる期間(本当に皆が外出を極力控え、家に籠っていた数か月)が懐かしいと思えるほど、僕たちは疫病とともに本当に長い時間を過ごしている。
YouTubeでライブカメラを頻繁に観るようになったのも、最初の非常事態宣言が出たころからだ。初めはすぐに検索で出てくる渋谷スクランブル交差点のライブカメラを観て、答え合わせのようにその人の少なさに驚いたりしていたけれど、慣れてくると次第に様々な土地のライブカメラを漁り観るようになった。いままで全然知らなかったが、ライブカメラは本当に世界中の様々な場所に設置されており、海の中から山の上、満点の星空から、どこかの街の人々の生活まで覗き見ることができてしまうのだ。YouTubeでは、動画をクリックするとたまに最初にCMが入ることがある。そうすると自分の気持ちはいっぺんに萎えてしまい、すぐに次のライブカメラへと移行することになる。CMの流れる間の十数秒のラグがいま現在、同じ世界で起こっていること、という現実感を奪ってしまう。すぐ横にあるサムネイルをクリックすると、激しい川の流れの中でちょうど熊が鮭を捕ったところが映し出された。すごい場面に立ち会ってしまったと思った瞬間に、左下に「HIGH LIGHT」の文字を見つけ、やはり気持ちは萎んでいく。僕はすごいものが見たいわけではなかった。何も起こらなくても良かった。物音ひとつしない部屋の中にいて、ただただ、いま同じ時間を生きている世界を観たかった。
ヘルシンキの港のライブカメラに行きついたのはたまたまだった。
僕にとってフィンランドはアキ・カウリスマキの国で、ヘルシンキは彼の映画の中にある街だ。パソコンの画面越しでもいまそこに街が存在しているリアリティが嬉しかった。
カウリスマキの映画を好きになったのはいつからだろう。最初は、小津安二郎に影響されたという、その無表情で妙な間を持った役者たちの変な演技がノイズだった。しかしいまではその妙な感じが癖になってしまった。
彼の映画の主人公はそのほとんどが貧しかったり、難民であったり、弱者という言葉で世間から安直に括られがちな者たちだ。彼らはぺしゃんこにされながらもゆたゆた立ち上がったり、ずるずる後退したまま、気づけば二、三歩前に進んでいたりする。カウリスマキはそんな彼らを絵画的に切り取り、洒脱と皮肉を交えながら、そこにあるグラデーションをリアルに描いていく。僕は作家の彼らに向ける目を信じている。

1996年のヘルシンキ。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ




