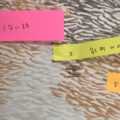笑いもの 第12回 「笑いの次に来るもの」
前回までは何かひとつ、自分が面白いと思ったものを取り上げて、笑いについて考えてきたこの連載だけれど、今回は何の手も借りず、愚直に笑いと向き合ってみたい。
というのも、この連載を通してつくづく思ったのは、笑いを語ることとは、僕の場合、どこまでいっても一種の自己言及に他ならないからだ。僕だけではなく、おおよそ何かを批評する人は、その対象を通して自分の内面を掘り下げているのだと思う。
だから、これからの文章はいままで書いてきた内容と重複する部分もあるけれど、そうした反復を繰り返すことでクリアになるアイデアもあるかもしれない。また、出来るだけ思考の寄り道もしてみようと思う。思わぬ拾いものは迷い道の路傍にこそある。
そもそも自分が笑いにこだわるのは、そこに世間とは違う逆転した価値観や破壊的なエネルギーを求めていたからではないか。このままならない世の中、笑い飯の言葉を借りると「思てたんと違う」世間に対して、何か痛快な一撃をかましたり、あるいは無責任な逃亡を果たしたい。人を笑わせると言うより、まず誰よりも自分が笑いたいという初期衝動。もっとも幼稚で、しかし切実なエゴイズムが根底にはある。
笑いは強烈なコンプレックスの裏返しでもある。特に笑いを生業にしようとする者は、結局のところ、そこにしか居場所を与えられなかったからで、だからこそあくまで笑わせることを矜持として、笑われることを極度に恐れるのではないか。笑いに潜む暴力に何より敏感なのは彼らかもしれない。
僕の場合も笑いは幼い頃からの避難場所であったり、コミュニケーションで優位に立てる数少ない武器だった。片親で貧乏で、成績が良かったのは中学までで、自慰を覚えてからはただのバカになった。腕力も度胸もなく、なんの取り柄もない僕は、ただ人とは違った本や漫画を読むことで自分を特別な誰かと思い込み、その暗示が解けない程度に、言い換えれば、身の程を知って傷つかないように恐る恐る世間へ混じっていった。
まったく自分の情けなさに反吐が出そうだけど、こうしたコンプレックスや自分自身への後ろめたさは誰にでもあるだろう。最近は自己肯定感の大切さがよく取り沙汰されるが、これは現代のネット環境があまりに先回りして、己の身の程を知らせてくることも関係あると思う。少しくらい絵がうまくても、歌がうまくても、顔が可愛くても、そんな優越感はスマホの画面をスクロールするだけで即打ち砕かれる。若いときは少しくらい自分に自惚れたり、根拠のない自信を持つ時期が必要かもしれない。ど田舎で育ったサブカル少年は情報の少なさによって自我を肥大させることができたけれど、いまの若い人たちはどうなんだろう? でも観察すると、彼らは彼らで無意識のうちに過剰な情報を遮断しながら、独自の自我を育んでいるようにも思う。もっとも若い自我などただの勘違いなので、いずれ修正を余儀なくされるものだけど。
僕は昭和の終わりに上京して、平成の始まりにギャグ漫画家としてデビューした。当時のギャグマンガは吉田戦車さんを筆頭に不条理ギャグが一大ブームを起こし、笑いの最先端は確実にマンガにあったけれど、それはダウンタウンの登場によってあっさり移行した。確かにダウンタウンの登場は鮮烈で、前世代へのカウンターとして用意された笑いは、当時のギャグマンガを引き継ぐ不条理さを備えながらも、ヤンキー独特のケレン味もあった。以前にも書いたけれど、ダウンタウンの成功は言うなればヤンキーの成り上がり物語で、だからこそ同世代の僕らは熱狂したはずだ。時代が違えばロックスターだったかもしれないし、場所が違えばラッパーだったかもしれない。才能は当然として、時代に合致した強烈な運の持ち主だけがカリスマになれる。
遡ればそれ以降、笑いと言えばお笑い芸人の「笑い」を意味するようになり、僕もごく自然にその視野の中で笑いを考えてきたように思う。しかし、ずっと違和感も感じていた。もともと不条理マンガでデビューした僕は、どちらかと言うと、どう笑っていいか分からないギャグの方が好みで、みんなが笑うギャグに笑えなかった。厳密に言うと面白いギャグはすでに構造が理解でき、そこに共感の笑いはあるけれど、自分が求めるショッキングな笑いは起こらないということだ。誤解を避けるために言っておくけれど、笑いの本筋はお客さんを笑わせることで、それができる芸人さんが偉いことに変わりはない。
しかし、舞台で起きる笑い、客席から声になって届く笑いは案外曲者だと思う。ライブでは何より、その場での爆笑が求められるので、シュールで微妙な笑いは「滑った」と誤解されることも多い。実際、ここ最近までシュールはつまらい笑いの代名詞だった。いまはランジャタイやDr.ハインリッヒの活躍によって、また演劇やコントの世界でもシュールな笑いが息を吹き返してる気がする。比べると昔のシュールは静的で、いまのシュールは動的に感じる。隙間ないデタラメによって一種のトランス状態を作り出すいまのシュールは、何事にも文脈を求めないいまの風潮にあっているのかもしれない。
話の時系列が入れ替わってしまったけれど、バブル後の先の見えない(それはいまも変わらない)閉塞感の中で、笑いがあれほど珍重されたのは、声となって聞こえる笑いが最も分かりやすかったからではないだろうか。例えば、美しさの価値はなかなか素人には判断できない。オークションで高値がついて初めてその価値に驚くものだ。しかし、笑いはその場で起きる。たとえ空気の振動に過ぎなくても、笑い声に包まれている間、人は先行きの不安と孤独を忘れることができる。当時の自信を失った日本人にとって、それは最も手っ取り早い現実逃避だったに違いない。
驚いたのはむしろ「笑い」の側だと思う。(ここから笑いを擬人化します)今までは権威に楯突き、モラルを破り、ただ野放図に振る舞っていた笑いがいきなり尊ばれ、諸手を上げて受け入れられたのだ。戸惑いつつもその旨味を知っている笑いは、にわかに手に入れた権威を守るため、あらゆる手を尽くした。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ