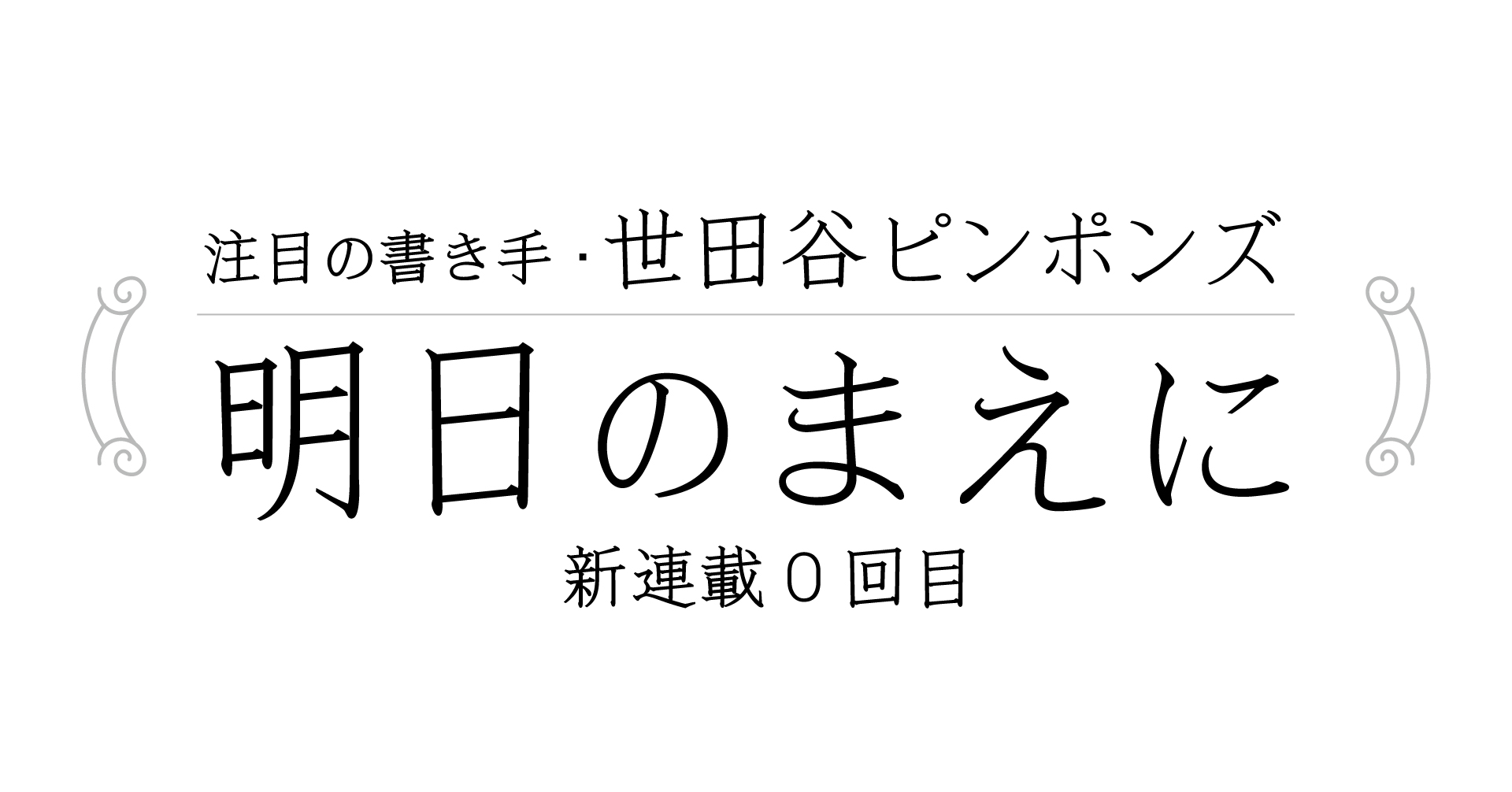フォークシンガー・作家として活動する世田谷ピンポンズによる新連載がスタートします。0回目の今回は、連載の内容をどうしようか、あれこれ考えあぐねている今の心境を綴ってもらいました。TV Bros. note版に書き下ろした短編も合わせて掲載!
『明日のまえに』
常日頃から「連載してみたいなあ。TVブロスとかめっちゃいいなあ」と思っていて、実際に口にも出していたから、お話を戴いたときには驚いた。たまに自分の引きの強さに驚くことがある。
世田谷ピンポンズという名前でフォークシンガーをしている。フォークシンガーというからには一人で活動しているのだが、たとえばどこかの街のレコード店に挨拶に行くと。
「こんにちは。世田谷ピンポンズと申します。新譜を展開してくださり、ありがとうございます」
「お疲れ様です。ところで今日はほかのメンバーさんはいらっしゃらないのですか?」
なんて、いるはずのないメンバーの動向を聞かれたりする。そりゃそうだろう。申し訳ないことだ。
「ソロで活動しております」ぼそっと答える。
その次にくるのが「東京の方ですか?」という質問。
「いまは京都に住んでいるんです」とまたぼそっと。
そして「京都なのに世田谷!」ということになる。
僕が東京にいるものだと思い込んでの仕事の依頼も多い。
ようやく分かってもらったあとにやってくるのが、なんて呼んだらいいのか問題。
「何てお呼びしたらいいでしょう?」
「そうですねえ。大概の人は世田ポン、ピンポンが多いですね。あと本名が細谷というので、本名の方で呼ぶ方もいらっしゃいます」
大概の場合はこの三つのうちのどれかに決まるが、中には自分で考えて決めてくれる人もいて、その場合は、世田谷さん、ピンポンズ君、世田ピンなどになる。中には世田谷ピンポンズさんなどと省略せずに呼んでくださる方もいて恐縮する。などなど色々ややこしくて、本名で活動している人に憧れたりもするけれど「良い名前ですね」と言ってくれる人も多くて嫌いにはなれない。いまではだいぶ定着してきた。
フォークシンガーとしての活動ももうすぐ十年になる。アルバムを作って、いろいろな街に歌いに行き、こうして文章を書いたりもする。
フォークというと「四畳半フォーク」ということばを思い浮かべる人が多いかもしれない。洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸がカタカタなるあの感じである。実際、僕も生活を題材に歌うことが多い。でもそれは貧乏礼讃とか、慎ましい二人の毎日が、とかいうよりは、いまの時代の空気を歌うという言い方がしっくりくる。あるとき、知人のミュージシャンに
「世田ポンはいまの時代のフォークだから四畳半フォークじゃなくて六畳半フォークだね」と言われた。
うまいことを言うなあと思って、それからはプロフィールに「六畳半フォーク」ということばを使うようになった。自分を端的に表しており、使い勝手がいいので方々で使っていたところ、ある日、別の誰かに「でも六畳半っていう間取りはないんだけどね」と言われて、ぎょっとした。確かに六畳はあるけれど、六畳半はない。途端に恥ずかしくなってしまい、ライブのMCで自虐的に言っていた時期もあった。でもよくよく考えると、このことば以上に自分を的確に表現してくれることばもないものだ。いまを歌う六畳半フォーク。それが僕の音楽だ。
何を書こうか悩んでいる。
僕は本が好きで、よく本屋や古本屋に行く。特に古本屋。下北沢古書ビビビは定期的にライブをさせてもらっている(コロナのせいでしばらくできていない)くらいに関係が深いし、訪れた街ではまず古本屋を探すのが癖になっている。御世話になっている古本屋のことも書きたい。面白い人たちが沢山いるのだ。
あと小説のこともいいなと思った。僕はいまの小説も昔の小説も大好きだけれど、特にずっと好きなのが昭和の私小説。上林暁や尾崎一雄のような自分やその周りの市井の人たちの生活を描いた作家の作品に惹かれる。地味でオチのない話が多かったり、ときにはなんでこんな会ったこともないおっさんの何十年も前の生活の愚痴を聞かなくてはならないのだろうと本気で思ったりするときもある。それなのに彼らの描く劇的ではない生活のなかに、人生の核心に迫ってしまうような描写(それはえてして、さりげないものであることが多い)を時折見つけてしまうから、たまらない。でもこれはかなり渋い題材だなあ。
喫茶店も好きだ。コロナ禍で外出もままならず、遠方の街にある喫茶店にめっきり行けなくなってしまった。そんなとき、かつて訪れた喫茶店のことを思い出すことは、久しく足が遠のいてしまっている街を思うことと直結していて、淡い。初めて訪れた街で喫茶店に入るのは、その街の水に体を慣らす儀式みたいなものだった。いまはそれができなくなって結構寂しい。
妙に落ち着くと思ったらソファーの柄が実家の物と同じだった京都・北大路堀川の『翡翠』、自分のドッペルゲンガーと遭遇した新宿西口の『ピース』、初めて訪れた日がたまたま閉店前最後の営業日だった地元の『アラジン』。旅行やライブで訪れた街にそれぞれそういう喫茶店があって、色々な思い出がある。それもいいな。
街や思い出について書きたいことはいくらでもある。感傷と僕とは仲のいい友だちで、いつでも僕は思い出してばかりいる。
昨年の十一月、夏葉社の新レーベル・岬書店から『都会なんて夢ばかり』という自伝的エッセイ集を出した。この本には僕の青春の街である東京・三軒茶屋を中心に、生活のことや音楽のこと、自分の恥ずかしい部分をほとんど噓なく書いた。さらけ出すなんて表現ができるほど波乱万丈な人生ではないけれど、独りぼっちだった大学時代からフォークシンガーとして活動していくまでの東京の日々を綴った。読んだ人からは「自意識丸出しで恥ずかしかった時代を思い出して、自分のことように読んだ」とか「いまは東京を離れたけど、本に出てくる東京での生活がいつかの自分の日々と重なって苦しかった」なんていう感想を沢山いただいた。みんな同じなんだな。とはいえ、本一冊分さんざん自分のことを書き散らしたのに、まだまだいくらでも書きたいことがある。
二六時中、昔のことを思い出しては、思い出の場所に思いを馳せ、実際にその場所を頻繁に訪れたりしている。何遍も訪れたら、思い出が薄まりそうなものだがそうはならない。むしろどんどん濃くなっていくから困る。
昔住んでいた太子堂のアパート。僕の注文だけ通っていなかった二条の鉄板焼き屋と、その帰り道に二人で見上げた大きな月。レンタルビデオを返却するときに使った道をなぞり、警官に職質されて自転車のブレーキが吹っ飛んだ場所をわざわざ見に行く。
歌ができてしまう。文章になってしまう。思い出すことは僕の背骨だ。 恥ずかしい姿をさらしている。じたばたしながら泳いでいる。又吉さんの『東京百景』、燃え殻さんの『すべて忘れてしまうから』、せきしろさんの『バスは北を進む』、尾崎世界観さんの『祐介』。センチメンタルの海は広い。そんな話が僕もまだまだ書きたい。
音楽のことも書きたいし、映画もいいな。いままで出会った沢山の人たちのことも書き残しておきたい。本当に書きたいことが多すぎて迷ってしまう。なんて贅沢な悩みだろう。思い出しては書いて、書いたことでまた思い出す。僕はこれからもそういうことを続けていきたい。

『サンライツ青葉台』
「ちん」
ひとけのない食堂にサトウのご飯を温め終えたレンジの音が鳴り響く。食堂は入寮するちょうど数ヶ月前に廃止され、今は機能していない。一応、キッチンは自由に使っていいらしかったが、料理をするような寮生を見かけることなど全くない。勝手が分からず必要以上に温まってしまったそれを指先で摘みながら、足早に自分の部屋に帰る。青葉台の男子学生寮。204号室。
二〇〇三年の春、僕は「上京」した。
初めて住んだ街・青葉台は横浜市の北部に位置するベッドタウンで、僕が入学した駒澤大学へは電車で三〇分くらいの距離にあった。
学生寮には自分と同じようにその沿線の大学に入学し、同じように生まれて初めての一人暮らしに対する期待と不安でいっぱいの友達がたくさんいるはずだ。自分のプライバシーなど全く省みられず、荒っぽくそれでいて熱に浮かされた慌ただしい大学生活が始まる。先輩に無理矢理飲まされたり、同級生と缶チューハイ片手に熱く語り明かす夜もあるかもしれない。恐れとほんの少しの期待を抱いて僕は入寮した。マイペースな方なので、自分の領域を侵されるのは嫌だったが、それ以上に高校の頃に謳歌できなかった青春を取り戻したい気持ちが強かった。引っ越しも終わり、両親は帰っていったが、そのときは寂しさよりも高揚感の方が大きかった。
次の日、早速、様子が違うことに気づいた。まず寮内を誰も歩いていない。風呂は共同の大浴場だったが、年頃の若者たちにとってがさつなくらい騒動の場所になるはずのそこにもせいぜい二、三人がいるだけ。それも無言で頭や体を洗ってさっさと上がっていく。無人のコインランドリーに洗濯機の回る音だけが響き渡る。食堂は真っ暗闇。手探りで電気をつけた。
若者どころかいきものの気配すら全くしない。電気がしっかりと点いて明るいのに、寮内は病棟のようなじっとりと陰気な気配に支配されていた。入口に設置された寮生の名前のパネルだけが彼らの在・不在を知らせてくれていた。
こんなはずじゃなかった。いきなりどこかのアパートでひとりぼっちになって寂しさを味わうよりはと選んだ学生寮が完全に裏目に出た。寂しいどころではなかった。
隣人とは入寮してすぐに一度だけ顔を合わせた。勇気を出して気さくに話しかけてみた。
「入学式はいつですか?」
「もう終わりました」
言うやいなや部屋に入り、鍵をかける隣人。
これが結局、寮で他人と交わした最後の会話になった。それから彼は僕が地元の友達と電話で話しているとすぐに壁を叩いてきて、こちらがやり返すとその二倍の量叩き返してくるのだった。こちらがその二倍返すと、またその二倍、といった感じできりがなく、いつも自分の方から折れた。そんなとき、ちょっと手が震えている自分が心底情けなかった。そんな陳腐な応酬だけが寮での他人との唯一のコミュニケーションになった。二年後、僕は寮を後にした。
あの頃、僕が一番恐れていたのは、何かを始めようとすると何かが始まってしまうということだった。一見矛盾するようだけれど、この感覚の支配下にあるために、まず電話をかけることができず、サークルに入れなかったし、アルバイトを始めることもできなかった。そのまま結局、大学でも友達作りに失敗した。僕は聖蹟桜ヶ丘に住む高校の友達を頼るしかなかった。行きたい場所には彼と行き、たまには居酒屋で飲んで、僕の部屋に泊まってもらうこともあった。それは新しく築けなかった憧れの大学生活の代替行為だった。何も起こらない東京での生活を一番恐れながら、一方では、知らず知らずのうちにそれを望んでいる自分が確かに存在していた。
「大学では自分から動かないと何も始まらないよ」叔父から言われた言葉をずっと反芻しているうちに大学時代はあっという間に過ぎた。
大学を卒業し、ようやく重い腰を上げて、一番やりたかった音楽を始めた。腰を上げるまでに四年もかかってしまった。本当に何をそんなに恐れていたのだろう。やり始めたら、また時間は転がるように過ぎていった。やることがあってもなくても時間はあっという間に過ぎていく。
上京して十八年。いまは東京を離れ、京都に住んでいる。東京には十年住んだ。その間には本当に色々なことがあった。コロナ禍前には東京での仕事が多く、そのたびに自分の思い出の街を訪れて感傷に浸るのが常だった。人よりセンチメンタルの出る量があきらかに多いから、いまも歌を作って暮らしている。
先日、学生寮のことが急に気になって、グーグルアースで調べてみた。記憶をたどりながら、思ったよりあの頃とほとんど変わっていない青葉台の街並みの先に、寮はまだあった。しかし、いまは名前も変わり、女子学生寮になっていた。間取りなどは全く変わっていなかったものの、内装は明るく好ましい感じに変わっていた。僕がひとりぼっちでサトウのご飯をチンしていたあの食堂では、いまは朝と夕に美味しそうな食事が出るらしい。
世田谷ピンポンズ●歌手、フォークシンガー。吉田拓郎や70年代フォーク・歌謡曲のエッセンスを取り入れながらも、ノスタルジーで終わることなく「いま」を歌う。
2012年『H荘の青春』でデビュー。今までにアルバム6枚、シングル3枚を発表。
2015年にはピース・又吉直樹との共作を発表し、注目を集める。
2020年、初の書下ろしエッセイ集『都会なんて夢ばかり』を岬書店より刊行。
音楽のみならず、文学や古本屋、喫茶店にも造詣が深く、今後様々な方面での活躍が期待されるあたらしいフォークの旗手。
エッセイ連載「ぶんがくとフォーク」( https://setagayapingpongz.goat.me/ )毎週土曜日21時更新中。
投稿者プロフィール
- テレビ雑誌「TV Bros.」の豪華連載陣によるコラムや様々な特集、過去配信記事のアーカイブ(※一部記事はアーカイブされない可能性があります)などが月額800円でお楽しみいただけるデジタル定期購読サービスです。