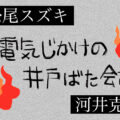TV Bros.WEBにて、連載『感傷は僕の背骨』を執筆している世田谷ピンポンズ。現在は京都に拠点を置き活動している彼が、東京でのライブのため上京してきたとのことで、世田谷ピンポンズ思い出の地である下北沢へ。古書ビビビやトロワ・シャンブルなどを訪れ、世田谷ピンポンズとは何者なのか、彼の中身を紐解いていく。

取材&文/笹谷淳介 撮影/飯田エリカ
取材協力:古書ビビビ
『感傷は僕の背骨』
撮影の前日、都内での久々のライブを終えた世田谷氏と待ち合わせたのは、下北沢にある古書店・古書ビビビ。彼が公私ともにお世話になっているというこの場所で撮影はスタートした。
早速、店内に入る世田谷氏。いつも入り口で店主の方に視線を向けて、その後に店内を回るそう。まず手に取ったのは、「車谷長吉の句集」。世田谷氏は車谷長吉が好きということで自宅には多くの本があるようだが、手に取った句集は持っていなかったようで、「撮影終わりに購入しようかと」と少し笑みを浮かべながら、満足気。そして慣れた足取りで店内を散策していく。
古書ビビビは、孤高のハイブリッド古書店として小説はもちろん、美術書や漫画、VHSなどマニアにはたまらない品を揃える、人気店。店先には、自主出版のZINEや最新作なども並ぶ。次に手に取ったのは、芸人・又吉直樹が編集長を務め、創刊された「又吉直樹マガジン 椅子」という雑誌。実は世田谷氏はこのZINEに椅子を題材とした曲の歌詞を寄稿している。
「なんてことない歌詞なんですけど…」と恥ずかしそうに掲載されたページを見せてくれた。

店内を回りながら、お話を聞いているとやはり文学や漫画などについての造詣が深い人だと感じた筆者は、世田谷氏にオススメの本を聞いてみると、少し悩みながら山川直人「地下室 初期の山川直人漫画集」と上林暁傑作小説集「星を撒いた街」をオススメしてくれた。

世田谷「『星を撒いた街』は昔の小説なんですが、夏葉社という出版社が復刊した本でして。最初、装丁が気に入って購入したんですが、作品自体が古書店に行くキッカケになった本なんです。山川直人さんは昔からファンです。数年前から親交もあり、お世話になっています。これは、オススメです!」
一通り店内を回ると、レジ前に到着し、店主の徳川さんと談笑する世田谷氏。親交が深まった理由は、自身のCDを置いてほしいと自らお願いに訪れたことがきっかけなんだとか。

話を終えて、次に世田谷氏の思い出の地・下北沢を散策しましょうと店を出る。長い間、三軒茶屋に住んでいたと話す世田谷氏は、三軒茶屋と下北沢をつなぐ茶沢通りがお気に入りの道なんだとか。「いつもこの道を歩くと涙が出そうなります(笑)」と若い頃の思い出に浸りながら、下北沢の街を歩いていく。
「どうでもいいんですけど、ここで自転車を盗まれました」、「ああ、ここは昔CoCo壱だったのにな」、「ここのライブハウスでライブをしたことがあったな」など次の目的地である、喫茶店・トロワ・シャンブルに着くまで思い出を回顧してくれた世田谷氏。道中には、よく足を運んでいたという、旧DORAMA(古本やゲームの販売・買取店)跡地にできたゲームセンターの前で写真をパシャリ。
あっという間の下北沢散策を終え、喫茶店・トロワ・シャンブル到着。取材日は暑かったこともあり、世田谷氏はアイスコーヒーを注文し、ひと段落。ここからは、世田谷ピンポンズとはどんな人間なのか紐解いていこうと思う。

――さて、今日は下北沢散策をしつつ、世田谷さんのゆかりある古書ビビビにお邪魔しましたが、改めて世田谷さんにとって古書ビビビとは?
オアシスのような場所ですかね。例えば、ライブで上手くいかなったときやなんやかやと身も心も削れたとき、ビビビに行けば優しくしてもらえて復活するというか。いちばんお世話になっている場所なのかなと思います。とはいえ、未だに店主の目を見て話せないんですけどね……(笑)。昔は、よく店内でライブをさせてもらったりとかご飯に連れて行ってもらったり、飲みに行ったり。僕のことをいつも応援してくださっています。今日は変なTシャツを着ていましたが、本当に優しい人です。
――あはは(笑)。今回は世田谷ピンポンズとは、どういう人なのかという少し世田谷さんのパーソナルな部分も聞いていきたいんですが、普段はフォークソングを歌われていますよね。キッカケはなんだったのでしょう?
そもそも音楽を好きになったのは、中学2年生ごろで。当時は、ゆずさんや19さんといった弾き語りデュオブームみたいなものがありまして。単純にいいなと思って憧れて。自宅にギターもあったのでひとりで歌って、曲みたいなものを作ってみようと思ったんです。そういった流れで、初期のゆずさんはフォークっぽい感じもありましたし、彼らのオールナイトニッポンを聴いていたときに、友部正人さんの“一本道” という曲が流れて、いいなと。それからCDを借りて聴くようになり、吉田拓郎さんや他のアーティストも好きになっていきました。
――なるほど。中学生の頃からフォークに傾倒するとなると周りには話の合う友人がいなかったのでは?
いやあ、全くいなかったですね。それこそ、周りにゆずを聴く友人もいなくて。当時はゆずさんが好きだったこともフォークが好きだったことも隠していました(笑)。ただ、ギターが弾けるということは知られていたので、ビジュアル系のコピーバンドに誘われたりとかはありましたね。
――ビジュアル系ですか?!
断ったんですけどね(笑)。黒夢さんの『少年』という曲のバンドスコアが友達の家にあったので、弾きこなしてしまったんですよ。そしたら「お前、やれんじゃん」みたいな感じになってしまって、あのときは危なかったですね。学生時代は音楽面では周りと分かり合えなかったです。
――そこからフォークをやっていかれると思うんですけど、当初はバンドを組まれていたんだとか?
最初期はそうですね。大学を卒業してから外に出て音楽をするようになったので、スタートは遅いんです。そもそもやらなくてもいいかなとも思っていましたし、やる勇気もなかった。でも、大学を卒業するタイミングで、mixiのメッセージで変な名前の人から連絡が来て、「趣味が合うと思うので、一度会いませんか」と言われバンドを組みました。
――mixiってコミュニティで趣味が判明しますもんね(笑)。それはフォークバンドだったんですか?
いや、銀杏BOYZが共通で好きだったので、僕はやるのであれば銀杏BOYZのようなバンドがやりたかったんです。でも、連絡をくれた彼は、銀杏BOYZに当時流行していたUKロック、ザ・ストロークスやザ・リバティーンズなどの要素を入れたいというビジョンがあったみたいで。僕はただただ暴れたかっただけだったので、上手くはいかず。途中で彼が脱退。他のメンバーも18歳や19歳で若くて、受験のタイミングなどで抜けていき、そこからひとりですね。当時、僕が24〜25歳くらいだったので、もう10年前くらいですね。
――そこから、世田谷ピンポンズとして歩み出すんですね。
バンドと並行して、ソロでやるときはなぜかこの名前で活動していたんですけど、いよいよ世田谷ピンポンズ一本になったタイミングはそこですね。
――ちなみに、由来はあるのでしょうか?
これは定かではないんですが、大学生のときどこにも発表しない自作の楽曲をひとりで作っていて、それをまとめて勝手にアルバムとか呼んでいたのですが、そのアルバムの名義として名前をつけたんです。三茶にずっと住んでいたので、世田谷で、ピンポンはおそらく松本大洋さんの「ピンポン」が好きだったところから着想を得たと思うんですが、“ズ”がついたのは僕も分からないです。こんなに“ズ”が足を引っ張ると思わなかったですね。
――確かに、“ズ”がつくことでグループだと間違えられることもありますよね?
グループには間違えられますね(笑)。当時、何を考えていたんでしょうね。未だよく分からないんです(笑)。
――世田谷さんの音楽って、“六畳半フォーク”と形容されていると思うんですが、これってすごくいい言葉ですよね。
最近、CMで吉田拓郎さんの歌を歌わせていただいたんですけど、「誰なんだよ?」ってなってて。それで、僕のプロフィールに六畳半フォークと書いてあるもんだから、それを見て「そんな間取りねえよ、六畳だろ」ってツッコミが見られるようになり、少し傷ついているんですけども(笑)。知り合いの方が言ってくれた言葉で、別に大した意味ではないんですけど、なんだか今っぽいなって思って。そのまま使っている形ですね。
――なるほど。かぐや姫など、“四畳半フォーク”と形容される方たちもお好きだったんですか?
どうなんでしょうか。僕が好きなフォークは吉田拓郎さんや友部正人さん、高田渡さんみたいな飄々としているフォークというか、そういった方たちが好きだったので、四畳半フォークにはあまり憧れはなかったかもしれません。でもそうすると“六畳半フォーク”と名乗るのも語弊があるかもしれないですね。
――今を歌っているフォークシンガーってことが分かる人には伝わるというか。
そうですね。知り合いも、きっとそういう意味で“六畳半フォーク”と形容してくれたんだと思います。とはいえ今を生きているから今を歌うことは当たり前なんですけどね……(笑)。
――個人的に世田谷さんは、歌を作るときと文筆されるときのボーダーがない方なのかなと思うんですが、いかがですか?
もともと、私小説が好きで、フォークにも生活を歌うことが多いという土壌があります。だから、文章にしても歌にしても自分のことを題材にというか日記のようなものというか。その時々、心が動いたことを書いているので、まっさらな物語みたいなものを考えたことがほぼないんです。上手く言えないですけど、自分の経験や感情をテーマにしている。普段はそういう感じですね。
――文筆業はどのタイミングで始められることになるんですか?
本屋との関わりが多いので、わりと前からちょこちょこエッセイみたいなものを頼まれたりすることもあって。もともと書くことも好きだったもんですから、大学のときはずっとブログを書いていました。その延長で自分のことを書くことが多いんですが、音楽と並行してそういうこともやっていきたいなと。そこから2020年末に夏葉社という出版社の中にあるレーベルというんですかね、岬書店というものがあるんですが、そこからエッセイ集を出すことになり、本格的に文筆業がスタートしましたね。
――なるほど。世田谷さんにこんなことを聞くのは野暮ですが、自分のことを赤裸々に書くって恥ずかしくないですか?
あはは(笑)。恥ずかしいですし、他人は興味がないんだろうなと思うんですが、そうやってずっと作ってきたので、そういうのが染みついちゃっていますね。誰の言葉かは忘れてしまいましたが、「個人的なことを書いたものにこそ普遍的なものが入っている」という言葉を見たときに自分のことを書いてもいいのかなって。その言葉が慰めになっているんですよ。
――世田谷さんの連載はまさしく、自分史のようなものだと思いますが、タイトルである『感傷は僕の背骨』に込めた思いはありますか?
僕は基本女々しいというか、とてもセンチメンタルなので。さっきも下北沢の街を歩きながら思ったんですけど、なくなっているものばかり目について、それを悔やむというか落ち込むというか。“感傷”という言葉自体にあんまりいい意味がないし、ネガティブなイメージがあるんですけど、考えてみると常に感傷が自分の中心にあったというか。ネガティブな意味で使われる言葉ですけど、自分の中心にある言葉なんだなと思って、いい意味で使ってみたいと思ったんです。久々に東京に来たら住んでいたアパートとか絶対見に行ったりするんですよ、僕(笑)。そういう女々しさも肯定したいんです。
――アパート見にいくのはすごく分かります。連載を執筆されるときはどのように書かれているんですか?
自分の薄い人生の中で、何かないかと。街を思い、何かなかったかなと探していますね。劇的なことが書ければいいんですが、そんなに劇的なことはないので、申し訳ないなと思っています。
――いやいや! 生きていて劇的なことなんて滅多に起こらないですよね。
いやあ、本当にないですよね。でも、歌の題材になったエピソードとかもありますし、何か強く心に残った思い出、それはエピソードではなく断片的に、あのときの誰かのちょっとした手の動きや誰々が言ったこと、変に覚えていること。これは自分の歌のコンセプトにもあることだと思うんですけど、心に残っていることを思い出しながら書いていっていますね。きっと、なんでそこまで心に残っているのか自分でも気になっているんだと思いますね。
――では、ある意味、断片的に何かあれば、書けてしまうということでもある?
だいぶ自分の中に残っているものがなくなってきましたけど(笑)。でも、そうですね。思い出して、書いているうちにまた思い出すという感じですかね。せきしろさんの「バスは北へ進む」という本の帯に、「思い出すために生きている」と書いてあって。自分のやっていることが腑に落ちるというか、その言葉にまた肯定されて、思い出して今も書いています。
――最後になりますが、今後、どういう連載にしていきたいですか?
東京を中心に書いていますが、今は京都に住んでいるし、そのほかの街にもライブでよく行くことがあるので、訪れた街のことを書いていきたいなと思っています。次、5月分ですかね? 昨年お世話になっていた歌手の先輩が亡くなられてちょうど1年になるので、その人のことを書けたらいいなと思っています。

世田谷ピンポンズ●歌手、フォークシンガー。吉田拓郎や70年代フォーク・歌謡曲のエッセンスを取り入れながらも、ノスタルジーで終わることなく「いま」を歌う。2012年『H荘の青春』でデビュー。
2015年にはピース・又吉直樹との共作を発表し、注目を集める。2020年、初の書下ろしエッセイ集『都会なんて夢ばかり』を岬書店より刊行。
音楽のみならず、文学や古本屋、喫茶店にも造詣が深く、今後様々な方面での活躍が期待されるあたらしいフォークの旗手。
最新楽曲『S・N・S・N・S』が各配信サイトで配信中。
京都 拾得 野村麻紀さんのこと【2022年5月 世田谷ピンポンズ連載「感傷は僕の背骨」】
投稿者プロフィール
- テレビ雑誌「TV Bros.」の豪華連載陣によるコラムや様々な特集、過去配信記事のアーカイブ(※一部記事はアーカイブされない可能性があります)などが月額800円でお楽しみいただけるデジタル定期購読サービスです。
最新の投稿
 大切な思い出がツバまみれ22024.04.17SLEEP FANTASY DREAMS(VIRGIN PRUNES)【2024年4月号 掟ポルシェ 連載】『大切な思い出がツバまみれ 2』
大切な思い出がツバまみれ22024.04.17SLEEP FANTASY DREAMS(VIRGIN PRUNES)【2024年4月号 掟ポルシェ 連載】『大切な思い出がツバまみれ 2』 「レイジ、ヨージ、ケイタのチング会(仮)」2024.04.13オカモトレイジ(OKAMOTO’S)、Yohji Igarashi、宮崎敬太 presents「レイジ、ヨージ、ケイタのチング会」18
「レイジ、ヨージ、ケイタのチング会(仮)」2024.04.13オカモトレイジ(OKAMOTO’S)、Yohji Igarashi、宮崎敬太 presents「レイジ、ヨージ、ケイタのチング会」18 未分類2024.04.10『押井守のサブぃカルチャー70年 YouTubeの巻』表紙イラスト担当 梅津泰臣画伯 YouTubeを語る!!
未分類2024.04.10『押井守のサブぃカルチャー70年 YouTubeの巻』表紙イラスト担当 梅津泰臣画伯 YouTubeを語る!! 感度ゼロからのスタート2024.04.03ミキ・亜生によるカメラ連載第9回「亜生の成長」後編
感度ゼロからのスタート2024.04.03ミキ・亜生によるカメラ連載第9回「亜生の成長」後編