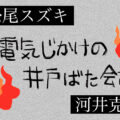文/布施雄一郎
この1年、コロナ禍の影響でライブを観にいく機会は激減してしまったが、23年前に30歳で上京し、音楽に関わる執筆を生業とするようになってから、本当にたくさんのライブを観てきた。今でこそ、特に仕事としてライブを取材する際にはディープな目線でステージを観ているが、もちろん以前はそんなことはなく、ただただ純粋に、そしてミーハーにライブを楽しんでいた。
そもそも10代の頃は地方に住んでいたため、好きなミュージシャンのライブ自体が少なく、「ライブに行く」ということは、本当に特別なもの。それこそ初めてロック系のライブを体験した時は、あまりの爆音に驚き、何の曲を演奏しているのかも聴き取れないほどであったが、それでも初めて体験するきらびやかなライティングに目を見張り、何よりも大好きなミュージシャンが目の前にいることに大興奮したものだった。たぶん、誰もが初めてライブに行った時と同じように。
そうした非日常のイベントとしてライブを楽しんでいた頃から、少しは音楽のことも分かるようになり、ちゃんとした耳で音を聴けるようになると、ライブの楽しみ方も少しずつ変わっていった。「生でミュージシャンを見られる場」であったライブが、「生でミュージシャンの演奏を体感する空間」に変わっていったのだ。
そうしたことを特に強烈に印象付けられた、いくつかの忘れられない想い出がある。
●高橋幸宏、HANAほか「Melody-Go-Round」
最初の強烈で決定的な想い出が、1993年に東京ドームで開催されたYMOの再結成ライブだ。当時は”YMO”の名称に”X”が付けられ、再結成ではなく”再生”という表現が用いられていたが、このライブの様子は今でもBlu-ray『TECHNODON IN TOKYO DOME』で観ることができる。
今でこそ、ライブにおける映像演出は当たり前のものとなっているが、この公演はそのハシリと言えるもので、巨大なマルチスクリーンには演奏と同期したグラフィックが投影され、ヴィジュアル面でも大きな話題となった一大ライブであった。しかし、筆者が受けた強い衝撃は、そこではない。3曲目に演奏された「FLOATING AWAY」の中盤だ。
この曲の冒頭、ドラムの高橋幸宏氏はスティックではなく、ブラシでスネアドラムをプレイするのだが、中盤でスティックに持ち替えると、8分音符のスネア連打から8ビートに切り替わるのだ。そのタイトなスネアドラムと、独特なちょっと跳ね気味のハイハット。それらが聴こえてきた瞬間、「うわぁ、幸宏さんが叩いてる!」と、脳が覚醒するかのように感動したことを、今でもはっきりと覚えている。
それまでも、幸宏さんが叩き出す8ビートは、レコードやカセットテープが擦り切れるほどにバカみたく何度も何度も繰り返し聴いていた。しかし、この時に感じた「目の前で叩いている(東京ドームなので、100mくらい離れた”目の前”ではあったが)」という初めての感覚は、いくらレコードを聴き込み、映像を繰り返し見ても得られない、ライブでしか体感できないものであった。
残念ながら、このライブでの同曲の演奏はBlu-rayで観て(聴いて)もらうしかないため、幸宏さんの8ビートを堪能してもらえる最新曲として、映画『音響ハウス Melody-Go-Round』主題歌を紹介したい。なお、ご存知の方も多いと思うが、昨年、幸宏さんは大きな手術をされて、現在は復帰に向けて静養中。また元気になられて、あのオンリーワンな8ビートを聴かせてもらえる日が少しでも早く訪れることを祈るばかりだ。
●大村憲司「リ―ヴィングホーム」
もうひとつ、ライブでの強烈な記憶は、大好きなギタリスト大村憲司氏のプレイ。あまりに当たり前なことすぎて、改めてここに堂々と書くこともはばかられるが、憲司さんのプレイを目の当たりにして、「プロってめちゃくちゃ上手い!」と心底感動したことだ。
冒頭でも触れたように、筆者は30歳を機に上京したわけだが、上京して最初に行ったライブが、憲司さんと、ギタリスト徳武弘文氏(with Dr. K Project)とのスペシャル・ライブだった。1998年4月。会場は、かつての新宿・日清パワーステーション。
幸宏さんの場合と同じく、憲司さんのギターも大好きでずっと聴いていたし、地方在住時代も、矢野顕子さんのライブなどにゲスト出演されていた憲司さんのギターを生で体験する機会はたびたびあった。しかしその時は、まだ自分の耳が未熟だったことに加えて、コンサートホールのステージと客席という距離感から、どこか別世界の出来事を客観的に観ているかのような感覚があった。それがこの日清パワーステーションでは、自分がミュージシャンと同じ空間にいるという感覚がもてたこともあり、じっくりと憲司さんのプレイを物理的にも心理的にも間近で堪能することができたのだ。
その時に感じた、ギターの艶やかな音色や繊細な演奏ニュアンス、そしてギターアンプで増幅される前の、ギター本体から聴こえてくるピックで弦をはじく生音。すべては、大村憲司という人が奏でている音だ。プロの凄さ、本物の素晴らしさを心底思い知らされた。
憲司さんは、残念なことに同年11月18日に、若くして他界されてしまった。その憲司さんを偲んで、後年に開催されたトリビュート・ライブでも、また忘れられない場面があった。
トリビュート・ライブには、憲司さんの盟友である村上”ポンタ”秀一氏も出演されていた。そのポンタさんが、ある曲の途中でタムを一発「タン!」と叩く。そこからリズムセクションが入ってくるという構成だったのだが、そのタム一発だけで、会場の空気が一変したのだ。たったひと叩きで、音楽の世界観を表現する。これもまさに本物の凄さに感嘆させられた瞬間だったが、そのポンタさんまでもが、つい先日、旅立たれてしまった。
そこでここでは、この本物のお二方、憲司さんと、そのバックでポンタさんがドラムを叩いている、とてもメロディアスな1曲を紹介しよう。憲司さんのオリジナル・インストゥルメンタル曲「リ―ヴィングホーム」。憲司さんが、故郷・神戸に想いを馳せながら書いたという、故郷を離れる歌だ。
●忌野清志郎「JUMP」
先に挙げたふたつのライブ・エピソードは、僕がまだライターとして仕事を始める前のものであったが、最後はちょっと番外編。ライターとなってから経験した、忌野清志郎氏に関する想い出だ。
実は筆者は、清志郎さんのライブを実際に観たことがない。そして、その機会を永遠に失ってしまった。しかし一度だけ、間接的にというか、特殊な形で一瞬だけ、清志郎さんを間近に感じたことがある。2008年のARABAKI ROCK FEST.だ。
僕はこのフェスに取材で行き、フェス2日目のヘッドライナーが、清志郎さんだったのだ(正式には、「忌野清志郎&NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNS」)。ただこの日、僕は最終の新幹線で帰京せねばならなかった。そこで、取材はヘッドライナー前のアーティストまでで無事に終え、あとは清志郎さんのステージを見て、速攻で仙台駅へと向かうという段取りだった。
ところが。悪天候も重なって進行が非常に押し、清志郎さんの登場時間が大幅に遅くなってしまったのだった。もちろんギリギリまで粘ったものの、最終の新幹線に乗るためには会場を離れざるを得ない時間となり、楽しみにしていた初めての清志郎さんライブを断念。泣く泣く仙台駅へと向かうバスの行列に並んだ。そして、ようやくバスに乗れる目途がついたところで、現地に残った取材チームに挨拶の電話を入れた。
その時だ。携帯電話越しに、取材チームの声の背後から「Oh Yeah!!!」という、あのシャウトと大歓声が聴こえてきたのだ。清志郎さんの声だ。清志郎さんが、そこにいる。心が震えた。
それが僕にとって、清志郎さんを直に感じることができた、唯一の体験だった。たったそれだけのことなのだが、それでも本当に貴重な体験ができたことを嬉しく思っているし、その想いは、年を追うごとに高まってきている。清志郎さん、存命であれば、今年で70歳。先日の5月2日が、12回目の命日だった。
現在、ミュージシャンは思うようにライブができず、音楽ファンも、ライブに行きづらい日々が続いている。ライブだけでない。スポーツ観戦も、美術鑑賞も、そして食事ですら制限が課せられ、本物を体感し、それが本物たる所以を知る機会がどんどん失われている。
いくら写真集や映像でピカソの名画を知っていても、油絵具に残された筆の跡や、その凸凹、さらには実際のキャンバスの大きさなどは、現物を目の当たりして、初めて知るものである。その驚きと感動は、この絵をピカソが描いている時の気配までをも想像させてくれる。本物を知るということは、想像力を掻き立ててくれるということであり、それが真に作品を体感するということだ。音楽において、本物を知る場というのは、やはりライブでの体感にほかならない。
そして人は、効率だけでは生きていけない。いくら栄養剤だけで生命を維持できる世の中になっても、やっぱり人は美味しいものを楽しく食べたいし、記念日には、普段とは違う御馳走を食べて祝おうという気持ちになる。ただ生きていられればいいのではない。喜びと安らぎを与え、感情を揺さぶり、心を豊にしてくれるものは生きていくうえで、とても大切なものだ。少なくとも、大切に思っている人の気持ちをないがしろにしてはいけない。
そういった、たくさんある“大切なもの”の中のひとつが、音楽であり、その音楽を奏でるミュージシャンの息遣いを直接感じとることができるライブという空間は、何ものにも代えがたい、そして、決して失ってはならないものだ。
今は、気軽に人と会うこともできず、旅に出ることも難しい。しかし、それが出来る日がきたときには、出来るだけ会いたい人に会い、聴きたいもの、観たいものは、可能な限り、ためらわずに体験して欲しい。その記憶は、必ず一生の宝物となるはずだ。
ふせ・ゆういちろう●音楽テクニカルライター。テレビブロスではサカナクション特集などで執筆を担当。https://twitter.com/MRYF1968
投稿者プロフィール
- テレビ雑誌「TV Bros.」の豪華連載陣によるコラムや様々な特集、過去配信記事のアーカイブ(※一部記事はアーカイブされない可能性があります)などが月額800円でお楽しみいただけるデジタル定期購読サービスです。