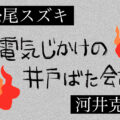シン・爆笑問題「ぼくたちYouTubeを始めました!」【前編】
シン・爆笑問題「ぼくたちYouTubeを始めました!」【後編】
<紙粘土・田中裕二>
キャンドル イン ザ ウインド

ここのところキャンドル・ジュンさんが話題だが、このニュースを扱うとき、どこかの番組できっとエルトン・ジョンの「キャンドル イン ザ ウインド」を流すだろうなと予想していたら、なんとサンジャポで流れた。
<文・太田光>
ともしび
波の音だけが聞こえている。
向こうはただの漆黒だった。人を吸い込むような恐ろしい空間。
昼間は穏やかな海が時に全く別の顔を見せることを少年は嫌というほど知っていた。
夜の海は少年にそのことを思い出させる。
今、その黒い海の手前に、小さな光が一つずつ、少しずつ灯っていた。その光は海に飲み込まれたたくさんの人の命の証明のようで、ずっと見ていると胸騒ぎのようなものが徐々におさまり、とても綺麗で、気がつくと少年の精神は穏やかになっていた。
怖いだけの海がその無数の光によって、鎮められているようだった。
大勢の近しい人を失い、これからどうして生きていこう。何の光も見えず、行き場を失い、いっそ無くなってしまったほうが楽かもしれない。母親がそう考えてるような気がして、少年は不安でしかたなかった。
しかし、今、目の前の無数の小さな光を見ている母親の目はキラキラと光って、その表情は安心したような笑顔になっていた。少年は嬉しくなって母親の手を強く握ると、母親もしっかりと握り返してくれた。
帰り道。
「綺麗だったね」と微笑む母親の笑顔は綺麗だった。
少しして、「かんばろうね」と母親が言った。少年は大きく頷いた。
そして、母親をこんなふうに元気にしてくれたあの光と灯してくれた人に、心の中で、ありがとうございます、と唱えた。あの光は命の恩人だと思った。
あれから十年以上の月日が流れた。
母親は光のイベントがあるたびにそこに訪れ、勇気づけられて帰って来た。
「今日も綺麗だったよ」「明日からまたがんばろう」と何度も繰り返して言った。
少年は、青年と呼ばれる年齢になった。
今もあの海の近くで暮らしている。
よく生きてきた、とたまに思う。よくここまで生きてきたと。
今、青年が見ているテレビでは、一人の男が記者会見をしている。
マイクを握り、涙を流し、マスコミと大衆に訴えている。自分にはいいが、家族に対する誹謗中傷はやめてくれと、もしそれが止まないならば、それを理由に自分が命を断つと言っている。
青年は目を閉じた。
「いっそ消えてしまおうか」
そう考えてきたに違いない、あの時の母親の表情がよみがえる。あの時の不安な気持ちが思い出される。
あの人をどうか、みんな守ってほしい。そして、母親に、今のあの人の言葉が突き刺さらないでほしい。あの光を希望に生きてきた母親に。あの人の子供達にも言葉が刺さらないでほしい。
あの光を消さないでほしい。
誰かがフッと吹いたら消えてしまいそうな小さな火。いつ消えても不思議ではない。それは命と同じだ。
「ケケケ」
どこからか突然ヘンテコリンな声がした。
見ると部屋の隅に、見たことのない奇っ怪な白い小さな動物がいて、ニヤニヤと笑っている。
耳は長くてウサギのようだが、顔は完全にネコのウサギネコだ。
「おまえ達は面白いニャぁ。っていうか、バカだニャ」
「何だと?」
「おれはずいぶん長いこと……何十年も、何百年もおまえ達人間とつきあってきた……ケケケ、おまえ達はちっとも変わらニャイ」
「お前は誰だ?」
「キャンドル・ニャンと言います」
「え?」
「……笑えよ!」
「……え?」
ウサギネコは顔をまっ赤にしてテレビに映ってる男にも言った。
「おまえも、笑え! 泣くニャ!」
青年は戸惑った。
「何だ、この動物は……」
「おれは見ての通りウサギだニャ!」
「ウサギ……何がそんなにおかしいんだ?」
「ケケケ、これが笑わずにいられるかニャ? おまえ達こそ、何を深刻ぶってるんだニャ……おれから言わせればおまえ達のバカは今始まったことじゃニャイ」
「どういうことだ?」