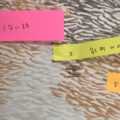第22回 結局、笑いとは?(前編)
「笑いとは?」という問いに対して、人はそれぞれ違う答えを返すだろうし、ひとりの人間の中でもその答えは気分次第で変わるだろう。
それだけ笑いはとらえどころがない、定義しようのない曖昧な概念と言える。否、笑いは概念というより、ただの現象かもしれない。
人は笑うとき、その意味を考えずに笑う。たしかに「考えオチ」もあるけれど、ほとんどの笑いは突発的であり反射的だ。
だから、笑いという感情の中には「驚き」という要素も混ざっている。しかし、笑いは驚きだけではない。ただ驚くだけなら、びっくりして終わりだ。
バナナの皮ですべる瞬間、人は笑わない。バナナの皮ですべる人を見て笑うのだ。
この典型的な例の中には笑いの本質が含まれている。
まず「バナナの皮ですべる人」を笑う人の中には、それが自分じゃなくてよかったという安堵がある。いままさにワニに襲われている人が、バナナの皮ですべっている人を笑う余裕はない。身の安全が確保されていること、これは笑いの条件の中で最も大切なものだ。
次に「バナナの皮ですべる人」が誰であるか、これで笑いの熱量が変わってくる。当然、バナナの皮ですべる人は普段威張っている権力者の方が面白いわけで、これが足下のおぼつかない老人ならただ心配になるだけだ。浴衣の老人がすり足でバナナの皮に近づく様子を見た場合、ほとんどの人は皮の手前で老人を止めるだろう。特に現代において老人の転倒を笑うことは犯罪に等しい。
権力が覆り、普段自分たちを抑圧しているシステムが一瞬無効になる。この開放感に気づいたとき、「近代の笑い」は誕生したのではないだろうか。詳しい考察をするほどの知識は持ち得ないが、国家の近代化とメディア革命が人の価値観を根本から刷新しただろうことは想像に難くない。
映画のスクリーンという安全な幕を通して、権力者を翻弄するチャップリンを笑うことは、当時の人にとってはまったく新しいエキサイティングな体験だったに違いない。
社会や時代を批判した大きな笑いと、そこに生きる人の慎ましい笑いをチャップリンは両立させる。けれど、詰め込んだというわけではなく、両者が響き合うことで深みのある笑いを生んでいる。
チャップリンの作品はエモーショナルな感動に満ちているが、そう誘うのはシニカルな視座に貫かれた脚本である。ただし、この時期の映画はサイレントなので台詞はない。すなわち脚本とは構成と同義であった。
書き手側からすると、笑いは構成がすべてだ。役者が変わっても台詞が変わっても、そこで何が起きたか、それが何を意味するか、あるいはしないかを観客は感じ取っている。というよりも、そう信じて書かざるを得ない。いくら本番では考え抜いた展開より、役者のアドリブが爆笑を取ったとしても。
自分にとって面白いものが、他人にとって面白いとは限らない──この当たり前の事実が自分を苦しめたり励ましたりする。
自分の感覚を他人と共有できないのは寂しい反面、それはまだ開拓されていない笑いの領域とも言える。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ