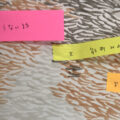笑いもの 第八回

▲僕が手がけた投稿企画の単行本たち。左上から『こどもの発想』『味写道』、左下から『書き出し小説』『バカはサイレンで泣く’09』
笑いにプロアマの差はない。どころか、その飛躍力と破壊力においてプロがアマに勝てるはずがない──と、信じていた。
もっともプロの笑いは血の滲むような経験と試行錯誤によって掴んだ「芸」であって、アマチュアの思いつきとはまるで異なる。だから最初から土俵が違うのだが、まだ二十歳そこそこのギャグマンガ家にそんな分別はなかった。自分が信じる「素人最強説」を実証するためにも、投稿企画の立ち上げは必然だった。
現在もつづく週刊SPA!の投稿ページ『バカはサイレンで泣く』はお恥ずかしながら、もう連載30年になる。当時生まれた赤ん坊が30歳に、100歳だったお年寄りは130歳になるわけだ。20代だった自分が50代になるのになんの不思議もない。ただ外見だけは老けたものの、中身の成長は我ながら全く感じられない。バカサイは自分にとって、男だらけの竜宮城といった感じだ。
最初は知り合いのライターさんが持ちかけてくれた話だった。
週刊SPA!のモノクロページを好きに使っていいから、なにか企画を考えてくれというものだった。当時のSPA!は、中尊寺ゆつこ先生が「オヤジギャル」で一世を風靡した後で、小林よしのり先生が『ゴーマニズム宣言』を連載したり、メジャーとサブカルを行き来するもっとも勢いのある雑誌だった。
ざっとSPA!を流し読んだ僕は、すぐに投稿企画がないことに気づいた。『ジャンプ放送局』や『ファミ通町内会』然り、ビックリハウスの『ヘンタイよいこ新聞』に宝島の『VOW』然り、面白い雑誌には必ずその片隅で異彩を放つ投稿コーナーがあった。僕は早速投稿ページを提案して、それは驚くほどあっさり認められた。
声を掛けてくれたライターさんがメンバー二人じゃ寂しいので、お互いもう一人ずつ集めようということになった。ライターさんが連れてきたのが山田ゴメスさんで、僕が声を掛けたのが同い年の椎名基樹だった。
椎名との出会いはテレビブロスの電気グルーヴ特集で、たしか女装サロンの体験企画だった。椎名がライターで、僕はなぜか電気の二人と女装する役を仰せつかった。卓球さんと僕は爆笑するほどのブスに仕上がり、チャイナドレスの瀧さんが、逆に男らしくなったことが印象に残っている。
椎名は電気の地元の後輩で、オールナイトニッポンの構成作家をやっていた。電気のオールナイトと言えばいまだに「これで道を踏み外した」「間違った価値観を受け付けられた」など称賛の声が止まない、ある世代にとっては計り知れない影響を与えたラジオ番組だ。僕も『人生(電気グルーヴの前身)』時代からのファンとして毎回正座で拝聴していた。
椎名を引っ張り込んだのは、そんな電気とのつながりもあるが、彼に自分と同じ野良犬の匂いを感じたからだった。
こうして勢いのみではじまったバカサイだが、当然ながら初回から投稿があるわけではない。募集期間の空白をどうしようかと考えた挙げ句、思い切ってすべて自作自演のヤラセネタを載せることにした。
なにせ募集前からネタで埋まった投稿ページである。おそらく読者は一発でヤラセだと分かるだろうが、面白いと思えばノってくれるだろうと踏んでいた。リアクションはすぐにあった。バカサイは開始二カ月ほどで大量にハガキが届くようになり、それは僕らのヤラセネタより断然面白かった。
冒頭の素人最強説は見事証明されたかに思えた。ただ、されたらされたで悔しい気もする。このあたりの自己矛盾がお笑い志向の面倒臭さなのだが、いったいなぜ、彼らの発想はこうも自由で面白いのか、考えざるを得なかった。
ひとつは「技量の制限を受けない」ことがあると思う。プロは芸人にしろマンガ家にしろ、思いついたアイデアを舞台や紙面に落とし込む過程が生ずる。煎じ詰めれば、その過程で発揮される「技」こそがプロの所以だ。しかし、素人はただネタを書き記すだけでよい。まるで神のように。
もっともシンプルだからこそ、その書き方には技が必要でセンスも問われる。いいネタは面白さだけでなく、その向こうに投稿者の人柄まで透けて見えるのだ。しかし、とりあえずは言葉だけで成立する投稿の気軽さが、彼らのイマジネーションをより自由にしている気がする。
もうひとつは「よりパーソナルな情報を織り込める」ことだ。プロはアイデアをよりよいバランスで、世間と共有できるよう擦り合わせなければならないが、素人はそのボーダーを大胆に踏み越えることができる。そして極めてローカルな話題であったり、パーソナルな心情は得てして共有より深い、共感を生むことがある。そんな一握りのプロ以外の、無限の多様性に触れることが、投稿企画の醍醐味だったりする。
ともあれ二つに共通するのは、プロでは許されない「無責任さ」が根底にあることだ。報酬のない彼らは、その代わりほとんど制約のない立場で(いまのご時世は制約だらけだけど)、自分のネタを晒し快感を得ている。それがたまらなく羨ましかった。
どんなジャンルでも言えることだと思うが、好きなことを仕事にすると、知らないうちにそれを続けるためのルールだったり、自主規制に縛られるようになる。そのぶん技は磨かれ、見える世界も広がるのだろうが、一番最初にその道を志したときの初期衝動は次第に色褪せ、ただ課せられた仕事に没頭するだけになる。
たぶん刀鍛冶や伝統工芸士なら、それでいいと思う。というか、そうあって欲しい。でも笑いに関わる身としては、それは唾棄すべき保身だと思うし、そもそも笑いという実態のないものを仕事にする時点で、やましさを感じる方がまともな気がする。
地元で一番面白いやつは、たいてい地元を出ないまま、意外と地味な仕事に就く。勇んで田舎を飛び出すやつは、実はたいして面白くない、ただの目立ちたがり屋かもしれない。
僕にとって投稿者は、一生追いつけない友達への憧れと重なる。
話が少し内省的になってしまった。
それにしても30年も同じコーナーをやっていると、そこから見える世相もある。
バカサイをはじめた当初は90年代前半で、バブル後の閉塞感もあって、笑いは加虐や自虐の色が濃かったように思う。小山田君の一件で当時の世相が取り沙汰されたが、サブカル界隈での露悪趣味は確かにあった気がするし、それをクールに受け止めるマナーのようなものがあった。
投稿者はアウトローが多かった。初めてイベントをやり投稿者に直接会うと、ハガキ職人というより労働争議の集会のようで、実際ニートよりブルーワーカーが多く、その中に十年近く浪人して東大に入った者や、新人キックボクサーや、愛人を連れたホテトル経営者がいた。ホテトル経営者のYさんはその後摘発されて、また新しい店を作ったからと言うので行ってみると、いかつい角刈りの本人がなぜか女装で接待してくれた。一体あれはなんの店だったのだろう。
元投稿者だったせきしろが、スタッフに加わったのもこの頃だ。
いわゆる大喜利的な笑いが定着したのは2000年前後だったような気がする。投稿で大喜利を始めたのはもっと前で、バカサイが最初だと思うけど、それは松ちゃんの一人ごっつを意識してだったのかもしれない。
一般の人からするとどうでもいい話だが、投稿シーンにとって大喜利の発明は正にエポックメイキングだった。それまで「コーナー」という緩い括りの中で募られていたネタが、「お題」という問題によって求められるようになったのだ。
考える方としては思考がよりフォーカスできて楽しいだろうけれど、常態化すると出題者と解答者の馴れ合いがそこはかとなく気持ち悪く思える。
笑いの競技化は結局、それを主催する者の思惑次第だ。毎週ハガキ選びをしている自分がなにをか言わんやだが、基本的に面白さの判断を他人に委ねるものではないという思いがある。
大喜利が定着し、ネットが普及することで笑いそのものはより拡充したけれど、同時に自閉的になったような気もする。みんながしたり顔で語るお笑い論はどこかで聞いた定説だし、「おもろい/おもろない」の線引きは芸人任せだ。
笑いそのものに息苦しさを感じた僕は、自分が心から面白いと思える素材を求めて、投稿企画の幅をさらに広げた。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ