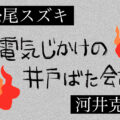<文・太田光>
最後の仕事
齢九十を超えた老人は、テーブルの上の一葉の写真を眺めていた。
若き日の自分と満面の笑みで握手をしているのは、ロナルド・レーガン。当時のアメリカ大統領だった。
写真を見つめる老人の目は心なしか柔らいだようにみえた。
「……貴方は、絵になる男だった」
ハリウッドで西部劇に出ていたというだけのことはあり見栄えがした。背が高く威圧感があったが、笑うとその笑顔は輝くようで、一瞬でその場の主導権と注目度を独占した。言葉にせずとも、主役は私だ。というように。
四十年近く前になる。
冷戦。東西の緊張は極致にまで高まっていた。米ソの軍拡競争は精神的にも経済的にも限界まできていた。世界中の人々が、いつ核戦争が起きても不思議ではない。と、常に覚悟していた。
老人はジッと写真を見つめている。
「……あの時貴方と私は、世界の注目の的だった」
ロナルド・レーガン大統領と対談する必要がある。
そう決めたのは彼だった。
第二次世界大戦後。共産主義の国であるソヴィエト連邦と、自由主義の代表であるアメリカ合衆国は二つとも核保有国であり超大国で、決して交わることがない敵対する者同士として世界に君臨してきた。
あり得ないと思われていた両国のリーダーの対面が実現したのは、スイスのジュネーブ。
奇跡のツーショットを世界中が驚愕の眼差しで眺め、熱狂した。
「あの頃の私達の仕事は、大したものだった」
二人で重要なことを確認しあった。
「核戦争は許されない。そこに勝者はいない。ソ連と米国は、軍事的優位を志向しない」
それはシンプルな思考だったが、実現するにはあまりにも複雑だった。
二人は何度も会い、グチャグチャに絡み合った鉄の鎖をほぐすように、丁寧に、大胆に共通の目的に向かい、ひとつひとつを解いていった。それは困難な作業だった。
二人は時にお互いの誤解を解かなければならなかった。
「あなたが先生ではないし、私が生徒ではない」
レーガンは彼より二十歳も上だった。時としてその態度は子供を諭すようになる。彼は父のような大統領に何度もそう言わなければならない場面があった。
「もちろん」そう言ってレーガンは笑った。
「わかっています。私は自分の立場を説明しているだけだ」
それでもアメリカとレーガンは、自分と自分の祖国に、気がつくと教えるという立場を取りたがった。その度に「我々は対等である」ということを念押ししたものだ。とはいえ、二人の関係は概ね良好だった。どちらも何としてもこの会談を成功させなければならないという強い意思があった。互いの家族を紹介し合い、酒を飲み、散歩もした。そして根気よく話し合った。
大陸弾道ミサイル・戦略爆撃機、中距離核戦力・戦略防衛構想。
互いの国の内部からもいくつもの妨害があったが、その都度二人でとことん話し合い、大国のプライドや意地を捨て、軍縮、核撤廃という青臭い目標に向かって政治生命を、いや、自分自身の生命をかけた。
世界は二人が次々と成し遂げていくことを奇跡を見つめるような目で見守り続けた。
INF全廃条約調印。
共同声明では、世界中が歓喜し、互いに祝福し合った。
人類の喜びの手応えを確かに感じた。歴史は大きく転換し、新しい時代に入るのだ。人類滅亡の不安はなくなり、世界は真の平和をようやく手にしたのだ。人間は、よちよち歩きの子供から、ようやく分別のある大人へと成長したのだ。
それまで世界を覆っていた黒い雲が一気に晴れて青空が見えていくようだった。
今、テレビでは老人の祖国の現在の指導者が演説している。それはとても攻撃的なメッセージだった。対するアメリカの現在の指導者もまた、応戦する形で強い言葉を発している。
「我々の頃とは違う」
老人は、テレビに映るよく知る現在の指導者を見つめた。
彼と初めて会ったのは、いつだったか。
痩せて、眼光の鋭い青年だった。直立不動で自分に敬意を表していたが、鋭い目の奥には、一瞬敵意が見えたような気がした。しかし、この青年がこれからこの国を率いていく人物になるだろうことは、瞬間的にわかった。
テレビの中の男は、痩せっぽちだったあの頃とは見違えるように逞しくなり、貫禄があった。
戦闘は続いている。爆撃を受けた町が映る。
老人はテレビから目を逸らし再び写真を見る。
「見てくれ。私と貴方の仕事が壊れようとしていく。私達が作った世界が……」
老人は深くため息をつき、シワだらけになった自分の手を見つめ、再び写真の中で握手している相手を見た。
「貴方はこの世界を見ずに済んで羨ましいよ。カウボーイ。どういうわけか……私は長生きをしすぎたようだ」
「ケケケ、弱気だニャぁ」
突然、ヘンテコリンな声が聞こえた。
見ると部屋の隅っこに奇っ怪で白い小さな動物がいて笑っている。
耳が長くてウサギのようだが、顔は完全にネコのウサギネコだ。
「お前は?」
「ケケケ、ウサギだニャ」
老人はジッと見る。
「ネコだろ」
「失礼ニャ! どう見てもウサギだニャいかストロイカ!」
「何を言っているんだ?」
「ケケケ、どうでもいいニャ! おまえ、ずいぶん弱気じゃニャイストロイカ?」
「ふざけてるのか?」
「まぁニャ」
「……ふん。弱気か……確かにお前の言う通りだ。私はもう老いぼれだ。まさか人生の最後にきて、自分が成し遂げたものを否定される姿を目撃することになるとは思いもしなかった。誰だって弱気にもなるさ」
「でもまだ生きてるニャ」
老人は力なく笑う。
「これが生きてるというならばな。私にはもう何の力もない。日がな一日こうして、テレビで、自分の過去の功績が破壊されていく様子を見ながら、何も出来ずに死を待つばかりの毎日だ。お前なんかにこの気持ちがわかるか?」
「ケケケ、おれにわかるわけニャイニャ。テレビの中の連中に聞いてみるんだニャ」
「何?」
画面には空爆を受け、瓦礫と化した町で血を流し、ボロきれのような服を着て、泣き叫ぶ赤ん坊を抱いた母親が、『誰かこの子を助けて!』と、叫び続けている様子が映し出された。
「あそこにも、ニャにも出来ずに死を待つばかりの人がたくさんいるニャ……おそらくおまえより先にその日がくるニャ」
老人は画面から目が離せなかった。
「ケケケ、お前たち二人の功績か。ケケケケ……笑わせるニャ」
ウサギネコは蔑むように笑った。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。有料会員登録はコチラ
投稿者プロフィール
-
太田光(おおた・ひかり)●1965年埼玉県生まれ。中でも文芸や映画、政治に造詣が深く、本人名義で『マボロシの鳥』(新潮社)などの小説も発表。
田中裕二(たなか・ゆうじ)●1965年東京都生まれ。草野球チームを結成したり、『爆笑問題の日曜サンデー』(TBSラジオ)などで披露する競馬予想で高額馬券を的中したりと、幅広い趣味を持つ。
最新の投稿
 天下御免の向こう見ず2025.04.22【2025年4月号 爆笑問題 連載】『♪蹴っても蹴っても蹴っても大好きよ~♬』『ドタバタ喜劇』天下御免の向こう見ず
天下御免の向こう見ず2025.04.22【2025年4月号 爆笑問題 連載】『♪蹴っても蹴っても蹴っても大好きよ~♬』『ドタバタ喜劇』天下御免の向こう見ず テレビブロス12月号龍が如く特集号2024.12.01【2024年12月号 爆笑問題 連載】『アレよさらば』『党首討論』天下御免の向こう見ず
テレビブロス12月号龍が如く特集号2024.12.01【2024年12月号 爆笑問題 連載】『アレよさらば』『党首討論』天下御免の向こう見ず テレビブロス10月号あいみょん特集号2024.09.17【2024年9月号 爆笑問題 連載】『どうの河野言っても月末には決まる』『総裁』天下御免の向こう見ず
テレビブロス10月号あいみょん特集号2024.09.17【2024年9月号 爆笑問題 連載】『どうの河野言っても月末には決まる』『総裁』天下御免の向こう見ず テレビブロス9月号地面師たち特集号2024.07.28【2024年7月号 爆笑問題 連載】『Uber Eatsで、いーんじゃない?』『都知事選』天下御免の向こう見ず
テレビブロス9月号地面師たち特集号2024.07.28【2024年7月号 爆笑問題 連載】『Uber Eatsで、いーんじゃない?』『都知事選』天下御免の向こう見ず