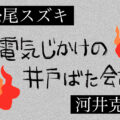<文・太田光>
ごっこ
テレビから聞き覚えのある音楽がオーケストラで流れて来た。
各国選手団の紹介とともに延々と入場が続く。競技場から花火が上がり、ドローンが空で地球の形を作る。
その日、男は何もすることがなく、部屋でラーメンを啜りながら、ぼんやりと画面を見つめていた。見るか見るまいか迷ったが、やはり見ることにした。
会場に見知った顔が何人か出てきて賑やかな衣装でコントを演じている。演技は全てセリフなしのパントマイムで表現される。
世界中が見守る舞台のパフォーマンスにおいて「言葉」は意味がない。体の動きや表情だけでいかに理解してもらうかが大切だ。パフォーマー達は大舞台でよく表現しているように見える。
言葉は時に凶器になる。自分がいくら意図しなくても人を傷つけることがある。
男は、ここ数日ずっと過去の自分を振り返っていた。若い頃から自分の表現をずっと考えてきた。思いつく色んな方法を試した。
いつからか、自分の表現では「風刺」や「社会批判」といった要素を扱わないようになった。善悪や正義の概念は時代とともに変わる。今作った作品はいつか色褪せる。自分は、いつの時代の誰から見ても瑞々しい作品を創りたいと思った。
言葉の表現と身体表現についてもよく考えたものだ。言葉は色褪せることがある。今の瞬間を切り取ったものだから。言葉で伝えることはわかりやすい。しかしわかりやすすぎる。メッセージ性を排除出来ない。意味のない言葉遊びのようなことも試した。それでも言葉の持つ強さは自分が表したいものを隠してしまう気がすることもあった。しかしどうしても自分の表現には言葉が必要だった。男はよく迷った。舞踊やパントマイム、あるいは言葉以上に「形」を重視した能、浄瑠璃もそうかもしれない。もっと簡単に言えば「しぐさ」だ。そうした身体言語は、10年後、20年後も変わらない。あるいは不滅かもしれない。男は試行錯誤しながら自分のコントから言葉を減らしたり、また足したりした。
男は自分の記憶を必死に呼び起こす。「もしかすると自分のいるべき場所は、ここではないのかもしれない」当時そう考えた時期があった。彼のいる場所は言葉が勝負の世界だった。他の大勢はひな壇と呼ばれる場所で、作品以外にいかに自分を出すかを争っていた。ここは自分には不向きだ、という思いがずっとつきまとっていた。
やがて彼は自分達だけの密閉された空間で表現をするようになっていった。不特定多数を相手に競い合うように表現する技術は自分にはないと思ったからだ。恐怖もあった。解る人だけがわかればいいと思ったわけでもないし、決して奢っていたわけではないが、口汚い同業者から『気取ってんじゃねえよ!』『格好つけやがって、スカしてんじゃねえよ!』という罵声も聞こえてきた。『アーティスト気取りかよ』と。そう言ったのは何とも下品なゲラゲラ笑いをする先輩芸人だった。
男は言い返すこともしなかった。確かにそう見えるだろうとわかっていた。確かに自分がやっていることはそう見えるだろう、と思った。「アーティスト気取りか……」。
アーティスト。
男は思った。確かに自分がやろうとしていることは世間では「アート」と呼ばれるものに近いのかもしれない。決してアートが高尚とは思わなかった。男は心から「笑い」が好きだった。だからそれを目指した。しかし自分が今やっているのは、いや、出来るのは“演芸”ではなく、“アート”と呼ばれているものなのかもしれない。
男は演芸を尊敬していた。畏敬の念すら抱いていた。しかしその世界は自分のいる場所ではないのかもしれない。
年々その思いは深まっていった。自分がここにいていいのだろうか? と。
男は舞台を降りる決意をした。自分は表に出ず裏にまわろう。そう決断するまでに何年もかかった気がする。
決断したあとは、今自分はどこにいるんだろう、と何度も考えた。自分は何者なんだろう、と。アーティスト? 演出家? プロデューサー? クリエイター?
男は漠然とした何者か、だった。これからは自分は何かを見つける試行錯誤が続くのだろう、と思っていた。
「ケケケ」
ヘンテコリンな声が聞こえた。テレビからだろうかと画面を見る。
テレビでは見知った顔がマイムをしている。
彼らを見て、男は幼い頃観て感動したサーカスのピエロのようだと思った。
ピエロはいい。誰も傷つけない。大人も子供も幸せに出来る。ピエロは言葉を発しない。言葉を発すれば誰かを傷つける。
そこまで考えてハッとする。今なぜ自分がこの状況にいるのかを思い出す。
男が過去に演じたコント。言葉を発しないはずの人物が発した言葉。その言葉が多くの人を傷つけた。そうか。あの時から自分は今日の自分を予見していたのかもしれない。自分には言葉を扱う技術なんてないと知っていたのに。あの時自分は奢ったのだ。自分の技術を過信したのだ。
「ケケケ、おまえは本当に理屈っぽいニャぁ」
今度こそ聞こえた。
男が声のした方を見ると、そこには奇っ怪で白い小さな動物がいた。耳が長くてウサギのようだが、顔は完全にネコのウサギネコだ。
「お前は、何だ?」
「ケケケ! ニャンだとは失礼ニャ! 見ればわかるだろう、おれはウサギだニャ! ケケケケ!」
「ウサギ?」
「そうだニャ! ケケケケ! おまえは悲劇の主人公か? ケケケ!」
その笑い方は、あの下品な先輩芸人にどこか似ていた。
「フギャ? あんニャ三流芸人と一緒にするニャ! 失礼だニャ!」
「え?」
「おまえの思ってることニャンか言葉にしニャくたってわかるニャ。おまえが残酷じゃニャイことも知ってるニャ」
男は驚いてウサギネコを見つめる。
この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。有料会員登録はコチラ
投稿者プロフィール
-
太田光(おおた・ひかり)●1965年埼玉県生まれ。中でも文芸や映画、政治に造詣が深く、本人名義で『マボロシの鳥』(新潮社)などの小説も発表。
田中裕二(たなか・ゆうじ)●1965年東京都生まれ。草野球チームを結成したり、『爆笑問題の日曜サンデー』(TBSラジオ)などで披露する競馬予想で高額馬券を的中したりと、幅広い趣味を持つ。
最新の投稿
 天下御免の向こう見ず2025.04.22【2025年4月号 爆笑問題 連載】『♪蹴っても蹴っても蹴っても大好きよ~♬』『ドタバタ喜劇』天下御免の向こう見ず
天下御免の向こう見ず2025.04.22【2025年4月号 爆笑問題 連載】『♪蹴っても蹴っても蹴っても大好きよ~♬』『ドタバタ喜劇』天下御免の向こう見ず テレビブロス12月号龍が如く特集号2024.12.01【2024年12月号 爆笑問題 連載】『アレよさらば』『党首討論』天下御免の向こう見ず
テレビブロス12月号龍が如く特集号2024.12.01【2024年12月号 爆笑問題 連載】『アレよさらば』『党首討論』天下御免の向こう見ず テレビブロス10月号あいみょん特集号2024.09.17【2024年9月号 爆笑問題 連載】『どうの河野言っても月末には決まる』『総裁』天下御免の向こう見ず
テレビブロス10月号あいみょん特集号2024.09.17【2024年9月号 爆笑問題 連載】『どうの河野言っても月末には決まる』『総裁』天下御免の向こう見ず テレビブロス9月号地面師たち特集号2024.07.28【2024年7月号 爆笑問題 連載】『Uber Eatsで、いーんじゃない?』『都知事選』天下御免の向こう見ず
テレビブロス9月号地面師たち特集号2024.07.28【2024年7月号 爆笑問題 連載】『Uber Eatsで、いーんじゃない?』『都知事選』天下御免の向こう見ず